「ハリスホークを飼いたいけど、鳴き声がうるさいって聞いたことがある…」
「SNSで見たハリスホーク、かっこいいけど実際の生活ではどうなんだろう?」
「近所迷惑にならないか心配…」
そんな不安や疑問をお持ちの方へ。

本記事では、ハリスホークの鳴き声の特徴やほんとにうるさいの、うるさい時の具体的な対処法について詳しく解説していきます。
猛禽類の中でも人気のあるハリスホーク。
しかし、その魅力の裏には「思った以上に鳴く」「声が大きくてびっくりした」と感じる人も少なくありません。
鳴き声への理解と対策をしっかり学ぶことで、ハリスホークとの暮らしをより快適に、そして長く楽しむことができます。
✅ 記事のポイント
✔ ハリスホークはよく鳴く鳥。
✔ 鳴き声にはストレス・空腹・環境要因など複数の原因がある
✔ 正しい対策をすれば鳴き声を軽減することが可能
✔ 飼う前に鳴き声の特徴を理解しておくことがトラブル防止につながる
ハリスホークはうるさい?

・他の猛禽類との鳴き声の比較
・鳴く時間帯やタイミングはいつ?
・実際の飼い主の口コミと体験談
ハリスホークの鳴き声ってどんな感じ?
ハリスホークは非常に知能が高く、感情表現も豊かな猛禽類です。
鳴き声も非常にうるさい時があり、「ピー」や「ギャー」といった高くて鋭い声を出すことが多いです。
特に、警戒時や興奮しているときには甲高く連続的に鳴くことがあり、周囲の注意を引きます。
また、空腹時や飼い主に何かを伝えたいときにも鳴き声を使うなど、非常に多用途なコミュニケーション手段となっています。
仲間のハリスホークと鳴き交わすことで社会性も保ち、グループで狩りをする習性にも繋がっています。
鳴き声のトーンやリズムは状況によって微妙に変化し、慣れてくると飼い主も意味を理解できるようになることがあります。
こちらが実際の鳴き声の映像です。
他の猛禽類との鳴き声の比較
ハリスホークの鳴き声は、フクロウのように静かなタイプではなく、むしろハヤブサやオオタカに近い鋭く大きな声です。
しかし、ハリスホークの個体差が大きく、中には非常におとなしく滅多に鳴かない子もいます。
一方で、人や音などに敏感に反応して頻繁に鳴く個体もいます。
特に家庭内で飼育している場合、外の車の音や他の動物の気配に反応して鳴くことがあり、自然環境と比べると鳴き声の頻度が高くなる傾向にあります。
猛禽類の中でも比較的社交的な性格を持つハリスホークは、音によるコミュニケーションが活発であり、それが騒がしく感じられる一因でもあります。
鳴く時間帯やタイミングはいつ?
多くの飼い主が報告しているのは、朝方や夕暮れ時など、活動が活発になる時間帯に鳴くことが多いという点です。
これらの時間帯は野生下でも狩りの時間にあたるため、本能的な行動とも言えます。
また、日常の中でルーティン化された行動、たとえば餌の時間や散歩の時間が近づくと、期待して鳴くケースもあります。
さらに、外で他の動物や人の気配を感じたとき、または自分の存在を主張したいときなども鳴く傾向があります。
飼い主の帰宅時や声をかけたときに反応して鳴く場合もあり、そうした鳴き方には愛着や関心の表れが見られます。
実際の飼い主の口コミと体験談
「朝の5時に毎日鳴くので、最初はびっくりした」
「家の前を人が通ると鳴いて知らせてくれる」
「静かな日もあるが、急に大声を出すと近所迷惑になることも」
など、リアルな体験談が多く寄せられています。
また、「感情が読み取れるほど、鳴き方に個性がある」といった意見もあり、ハリスホークの鳴き声は飼い主との絆を深める要素にもなっています。
とはいえ、騒音トラブルにつながることもあるため、周囲の理解や防音対策も重要です。
ハリスホークがうるさい理由

・空腹や欲求不満のサイン
・繁殖期や発情期による鳴き声の変化
・飼い主との関係性が影響することも
ストレスや環境による影響
飼育環境が適切でない場合、ハリスホークは非常に敏感にストレスを感じ、それが鳴き声として現れることがあります。
たとえば、狭すぎるケージに長時間閉じ込められていると、運動不足や不安からイライラしやすくなります。
また、周囲の音がうるさすぎたり、頻繁に人が出入りするような落ち着かない場所に置かれていると、警戒心が強まり、しばしば鳴いて自己防衛のサインを出します。
気温や湿度が適切でないと、体調にも影響を及ぼし、それが不快感として声に表れる場合もあります。
快適な環境づくりが、ハリスホークの鳴き声を抑える第一歩です。
空腹や欲求不満のサイン
ハリスホークは感情をストレートに表現する鳥です。
餌が不足していると「もっと欲しい」と訴えるように鳴き、運動不足のときには「外に出たい」「飛びたい」という気持ちを声に出します。
遊び足りない、または構ってもらえないことも欲求不満の原因になり、それがストレスと結びついてさらに鳴くことにつながります。
特に若い個体はエネルギーに満ち溢れており、刺激を求める傾向が強いため、日々の適度な運動や遊びの時間を確保してあげることが大切です。
繁殖期や発情期による鳴き声の変化
ハリスホークは繁殖期や発情期に入ると、本能的に鳴き声が激しくなることがあります。
この時期には異性を引きつけるために特有の声で鳴いたり、自分の縄張りを主張するために周囲に向かって大きな声を出したりする傾向があります。
これは自然な生理現象であり、無理に止めることはできませんが、時期を知っておくことで心構えができます。
場合によっては、繁殖期の間は静かな場所に移動させるなどの工夫が必要になることもあるでしょう。
飼い主との関係性が影響することも
ハリスホークは非常に知能が高く、人間との関係性に敏感です。
飼い主との信頼関係がしっかりしていないと、不安や寂しさから鳴き続けることがあります。
とくに飼い主が忙しく、あまり構ってあげられない状況では、注意を引こうとしてしきりに鳴くことがあります。
一方で、日々のコミュニケーションを重ねることで安心感を得た個体は、穏やかに過ごすことができ、無駄に鳴くことが少なくなります。
スキンシップや声かけ、アイコンタクトなどを通じて信頼関係を築くことが、鳴き声対策にもつながります。
ハリスホークがうるさい時の対処法

・適切な環境づくりとストレス軽減
・訓練やしつけでできること
・近隣トラブルを防ぐための注意点
・ハリスホークがうるさい まとめ
鳴く原因に合わせた対処法
まずはなぜ鳴いているのか原因を探ることが大切です。
鳴く理由は空腹、ストレス、不安、興奮、あるいは単にかまってほしいなど、多岐にわたります。
空腹の場合は餌の量や与える時間を見直し、十分に栄養をとれているか確認しましょう。
ストレスが原因であれば、生活環境の音や光、人の出入りの多さなど、周囲の刺激を減らす工夫が必要です。
また、日々のスケジュールを安定させることで、不安を軽減し、鳴き声を減らす効果もあります。
原因を特定するには、日記をつけるように観察記録を残すのも有効な方法です。
適切な環境づくりとストレス軽減
ハリスホークが安心して過ごせる環境を整えることは、鳴き声対策の基本です。
十分な広さのあるケージや屋外スペースを用意し、自由に羽ばたける時間を確保することで、ストレスを大きく軽減できます。
さらに、室内で飼う場合は、防音シートやカーテンを使用して外部の音を遮る工夫も重要です。
適切な温度と湿度を保ち、四季に合わせた微調整を行いましょう。
また、退屈しないようにおもちゃやパーチを用意することも効果的です。
私のおすすめのおもちゃはこちらです!
環境が快適であれば、自然と鳴く回数も減っていきます。
訓練やしつけでできること
ハリスホークは賢く、人間とのコミュニケーションもよく取れる鳥なので、しつけも可能です。
例えば、「鳴いても無視する」「鳴かないときにだけ声をかけたり、ご褒美を与えたりする」などの正の強化を活用すると、鳴き声の頻度をコントロールしやすくなります。
訓練を始める際には、まず短い時間からスタートし、徐々にステップを増やしていきましょう。
また、あまりにも過敏に反応してしまう個体には、鳴き声を抑える目的でリラックスできる音楽や自然音を流すといった方法も有効です。
ただし、すぐに成果が出るわけではないので、忍耐強く、焦らずに継続することが大切です。
近隣トラブルを防ぐための注意点
特に都市部や集合住宅での飼育では、鳴き声による近隣トラブルに注意が必要です。
事前にハリスホークの鳴き声の特徴や頻度を理解し、可能であれば近隣住民に説明しておくと良いでしょう。
さらに、ケージの周りに吸音材を貼ったり、ケージを窓から離したりして、外への音漏れを最小限に抑える工夫も効果的です。
また、鳴き声が大きくなりやすい朝や夕方の時間帯には特に注意し、その時間帯に遊びや食事の時間を設けることで、気をそらすことができます。
鳴き声に対して周囲の理解を得るためにも、SNSなどで日常の様子を共有するのも一つの方法です。
ハリスホークがうるさい まとめ

ハリスホークの鳴き声は、時に大きく、頻繁に鳴くこともありますが、それには必ず理由があります。
体調や気分、周囲の環境の変化など、彼らは繊細に反応し、鳴き声という形で私たちに何かを伝えようとしています。
鳴き声の背後にあるメッセージを正しく読み取るためには、日々の観察が不可欠です。
また、適切な対処法を知り、それを実践することで、無理なく静かな暮らしを実現することも可能です。
環境を整え、ストレスを軽減し、信頼関係を深めることで、ハリスホーク自身も安心して過ごせるようになります。
鳴き声をただの騒音と捉えるのではなく、コミュニケーションの一部と考えることで、より深い絆を築くことができるでしょう。
ハリスホークの魅力を理解し、その個性と向き合うことが、飼い主としての大きな喜びの一つです。
関連記事はこちらから!!




















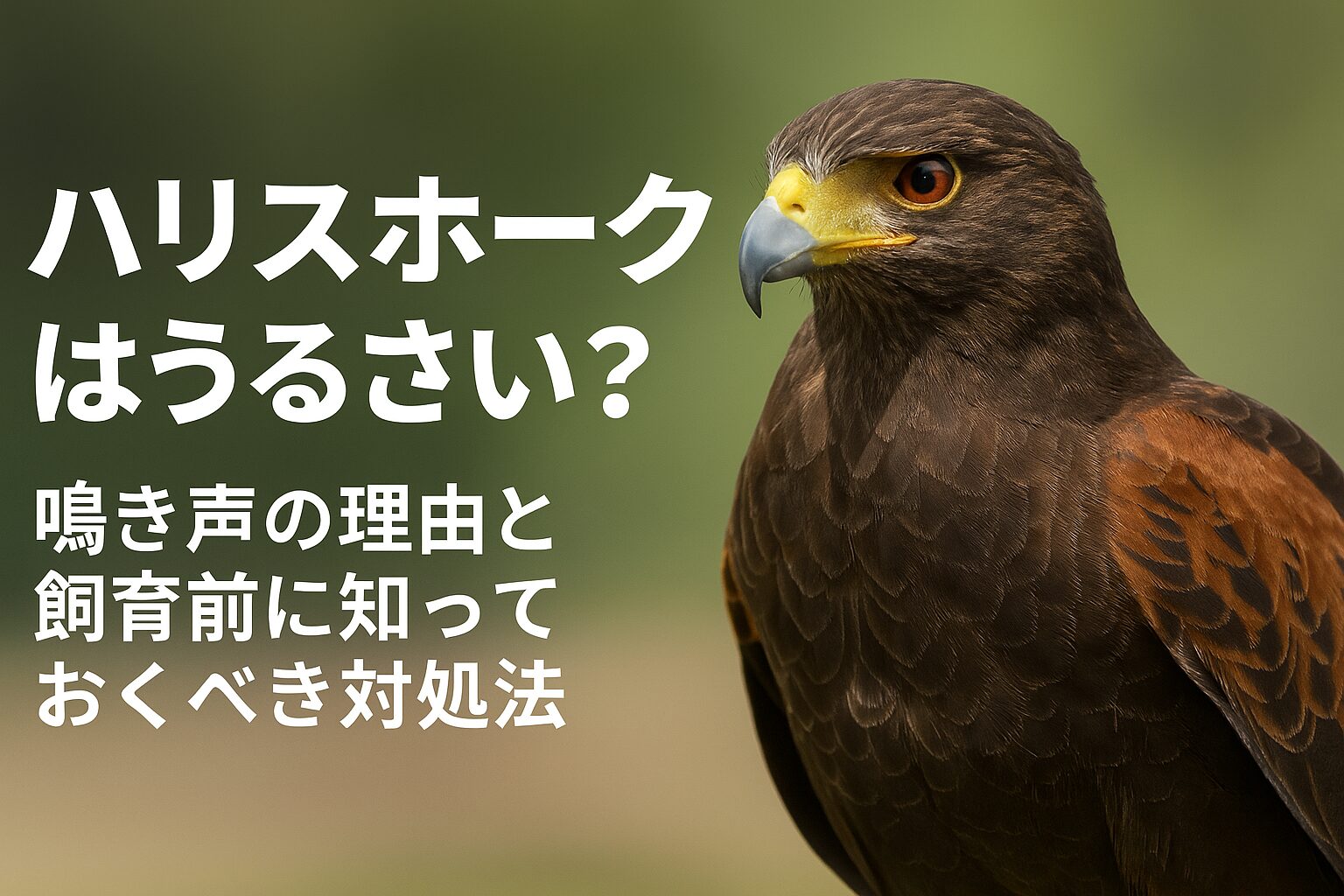

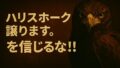
コメント