はじめての猛禽類ペットに憧れてチョウゲンボウを飼ってみたいんだけど、「他の鷹と比べて飼いやすいの?」
「ちゃんと懐くのかな??」と思っている方は多いはず。
SNSなどでは手に乗るチョウゲンボウのかわいい姿を目にすることもありますが、実際にペットとして迎えるとなると、性格・接し方・飼育環境などをしっかり理解しておくことが大切です。

この記事では、チョウゲンボウが人になつくのかどうか、なつきやすさの特徴、なつかせるための具体的な方法、注意点などを徹底解説します。
「チョウゲンボウはなつくのか?」という疑問に正しく向き合い、愛鳥との信頼関係を深めるための知識をしっかり押さえていきましょう。
記事のポイント
✔ チョウゲンボウは猛禽類の中でも比較的なつきやすい
✔ 幼鳥期から育てると信頼関係を築きやすい
✔ なつかせるには環境・接し方・根気が重要
✔ なつきすぎによるデメリットや依存にも注意
チョウゲンボウはなつくのか?

・チョウゲンボウの寿命
・チョウゲンボウの大きさ
・チョウゲンボウはうるさいのか?
・なぜチョウゲンボウは人気なのか?
・チョウゲンボウとなつく関係を築いた飼い主の体験談
・チョウゲンボウはペットとしておすすめ?
チョウゲンボウの生態
チョウゲンボウは、小型の猛禽類で、ヨーロッパ・アジア・アフリカに広く分布しています。
日本でも北海道から九州にかけての開けた草原や農地などで観察されることがあり、その姿は鳥好きや自然観察者に人気です。
主にネズミや小型の鳥、昆虫などを捕食し、優れた視力を活かして獲物を見つけます。
特徴的なのはホバリング(空中で静止する飛行)をしながら獲物を探す姿で、この飛び方がとても愛らしく、見ているだけで魅了される人も多いです。
自然との調和を感じさせる存在としても注目されています。
チョウゲンボウの寿命
野生下では約5〜10年ほど生きるとされていますが、捕食や事故、病気などのリスクがあるため短命になるケースもあります。
対して飼育下では、適切な温度管理、清潔な環境、バランスの取れた食事、そしてストレスの少ない接し方を維持することで、10年以上生きることもあり、中には15年近く生きた例も報告されています。
寿命を延ばす鍵は、健康管理と日常的な観察による早期の異常発見です。
チョウゲンボウの大きさ

チョウゲンボウは猛禽類の中でも小型で、体長は約30〜35cmほどになります。
体重はオスで約150〜200g、メスで180〜250g程度です。
このサイズ感は室内での飼育にも適しているとされ、初心者でも扱いやすいといわれています。
見た目は小さくても、筋肉質で機敏な動きをするため、狩りのパフォーマンスも見応えがあります。
小柄ながらも俊敏で、空中でのホバリング飛行が得意なのもこのサイズならではの特性といえます。
また、手に乗せても負担になりにくいため、ファルコンリー(鷹狩り)愛好家にも親しまれています。
チョウゲンボウはうるさいのか?
チョウゲンボウは普段はそれほど大きな鳴き声を発しませんが、警戒したときや求愛行動中には「キッキッキッ」といった鋭い声を出すことがあります。
特に繁殖期や見知らぬ人が近づいたときには、驚いて鳴くことがあるため注意が必要です。
飼育下では環境に慣れると比較的静かになりますが、完全に無音というわけではありません。
チョウゲンボウは警戒心が薄れるにつれて鳴く頻度が減る傾向にあります。
近隣への配慮が必要な場合は、防音対策を検討するのがおすすめです。
防音シートや設置場所の工夫によって、ストレス軽減と音の遮断が両立できます。
なぜチョウゲンボウは人気なのか?

チョウゲンボウはその美しい羽色と、小型ながら凛々しい見た目で人気を集めています。
オスは青灰色の頭部と背中、メスは褐色がかった模様が特徴で、どちらも見応えがあります。
また、他の猛禽類に比べて比較的おとなしく、人に慣れやすいとされる点も人気の理由です。
さらに、野生でも都市近郊に現れることがあり、その身近さから興味を持つ人が増えています。
観察しているだけでも飽きない、魅力に溢れた存在といえるでしょう。
チョウゲンボウとなつく関係を築いた飼い主の体験談
実際にチョウゲンボウを飼っている飼い主の多くが、「時間をかけてゆっくり接すれば、チョウゲンボウも心を開いてくれる」と語っています。
手からエサを食べたり、名前を呼ぶと反応したりする様子に、深い絆を感じるという声も多いです。
特に幼鳥から育てた場合は、人の手に慣れやすく、肩や腕に乗って休むような仕草も見られることがあります。
また、定期的に飛行訓練を行いながら信頼を築いていく過程を楽しむ飼い主も多く、その絆はペットというより相棒のような感覚だと言われています。
チョウゲンボウはペットとしておすすめ?
猛禽類としては比較的飼いやすい部類ですが、専用の設備、毎日のケアなどが必要なため、簡単に飼えるペットではありません。
猛禽類飼育の知識と覚悟が必要です。
特に日本では、猛禽類の飼育には都道府県ごとの規制があるため、事前に確認が欠かせません。
飼育には広いスペースや、飛行訓練のための設備、適切なエサ(冷凍マウスやヒヨコなど)が必要で、費用や手間もそれなりにかかります。
しかしその分、しっかり向き合えば、信頼関係を築ける貴重な存在となるでしょう。
チョウゲンボウはなぜなつくのか?

・チョウゲンボウがなつきやすい理由とその背景
・なつきすぎることのデメリット
・チョウゲンボウがなつかない原因とは?
人と信頼関係を築く鳥の特性とは?
鳥類の中でも知能が高いとされる猛禽類は、人との信頼関係を築くことができる種類もいます。
チョウゲンボウもそのひとつで、毎日の接触やエサやりを通じて、徐々に人に慣れていきます。
特に一貫性のある接し方や、飼い主の存在をポジティブなものと認識させることが、信頼構築の鍵になります。
猛禽類は犬や猫のような甘え方はしないものの、彼らなりの表現で信頼を示してくれるため、その繊細なサインを読み取る観察力も求められます。
チョウゲンボウがなつきやすい理由とその背景

小型で警戒心が比較的弱いチョウゲンボウは、人との距離が近づきやすい傾向があります。
特に若い個体から飼育を始めると、よりなつきやすくなります。
幼鳥の段階で人間に慣れさせると、人の存在を安心できるものとして受け入れやすくなり、日々のスキンシップやエサやりによって親しみが深まっていきます。
また、チョウゲンボウの性格には個体差があり、中には非常に人懐こい性質を持つ個体もいるため、性格に合った接し方をすることが大切です。
なつきすぎることのデメリット
なつきすぎた個体は、人から離れたがらなくなったり、外での飛行訓練を嫌がったりすることがあります。
また、依存が強くなることでストレスや健康管理にも注意が必要です。
過度に依存したチョウゲンボウは、飼い主が視界からいなくなるだけで落ち着きを失うことがあり、その状態が続くと食欲不振や体調不良に繋がる恐れもあります。
適度な距離感を保ちつつ、信頼を維持することが理想です。
独立性を促すためには、一時的な離れ時間を作るなどの工夫も効果的です。
チョウゲンボウがなつかない原因とは?
なつかない理由として、急な接し方や不適切な環境、信頼関係を築く時間不足が挙げられます。
また、個体の性格によっては、人間に対して強い警戒心を持つものもいます。
改善するためには、まずチョウゲンボウが安心できる環境を整えることが重要です。
静かな場所にケージを置き、急な動作や大きな音を避け、毎日同じ時間にエサを与えるなど、ルーティンを守ることで安心感を与えられます。
無理に触れようとせず、チョウゲンボウ自身のペースで距離を縮めることが、信頼回復への第一歩となります。
チョウゲンボウをなつかせるために

・チョウゲンボウとの信頼関係の築き方
・しつけ・エサやり・接し方のポイント
・チョウゲンボウを飼うのは大変?
・チョウゲンボウをなつかせるまでにかかる期間は?
・なつく個体・なつかない個体の違いとは?
・チョウゲンボウとの暮らしで後悔しないために
なつくための環境と飼育条件
なつくには、安全で静かな飼育環境が必要です。
広めのケージ、適度な日光、温度管理、飛行訓練スペースが理想的です。
また、ケージの中に止まり木を設置したり、羽ばたきができるスペースを確保することで、チョウゲンボウにとって快適な住環境が整います。
さらに、野鳥の鳴き声や自然の音が聞こえるような環境も、ストレスを軽減し、より安心して過ごせる要因となります。
突然の音やストレス要因を排除し、チョウゲンボウがリラックスできる空間を提供することが大切です。
チョウゲンボウとの信頼関係の築き方

毎日のエサやりを手渡しで行い、ゆっくりとした動作で接することが大切です。
声をかけたり、アイコンタクトを取ることで、少しずつ距離が縮まっていきます。
最初は人の気配に慣れてもらうことから始め、徐々に手を近づけたり、短い時間でも同じ空間で過ごすことで安心感を高めていきます。
また、同じ服装で接する、静かな声で話しかけるなど、チョウゲンボウが覚えやすい環境を整えることも、信頼を得るためのコツです。
しつけ・エサやり・接し方のポイント
エサは新鮮な肉を中心にし、訓練を兼ねたやり方(例:呼んだら来る、合図で飛ぶ)を取り入れると、なつきやすさが増します。
特にご褒美としてエサを与えることで、ポジティブな経験を記憶させることができます。
罰ではなく褒めて教える方法が効果的で、失敗しても怒らず、成功したときにしっかり褒めることで学習が進みます。
毎日のトレーニング時間を決めて規則的に行うことで、チョウゲンボウにとっても安心感が生まれます。
チョウゲンボウを飼うのは大変?
猛禽類を飼うには、専門的な知識が必要であり、毎日の世話にも手間がかかります。
エサの準備、清掃、健康チェック、飛行訓練など多岐にわたる作業が日課となります。
さらに、病気の早期発見や、ストレスサインに気づく観察力も必要です。
しかし、しっかり準備すれば深い絆を築ける魅力的な相棒になります。
飼い主が真剣に向き合う姿勢が伝われば、チョウゲンボウも応えてくれるでしょう。
長期的な関係を築く覚悟があれば、唯一無二の存在になること間違いありません。
チョウゲンボウをなつかせるまでにかかる期間は?

個体差はありますが、早ければ数週間〜数ヶ月である程度なついてくることもあります。
なつくスピードは年齢や性格、過去の経験に大きく左右されます。
例えば、幼鳥から育てた場合は早くなつきやすい傾向があり、成鳥を迎える場合は慎重に時間をかけて関係性を築く必要があります。
焦らず根気よく接することが何より大切です。
日々の積み重ねが信頼に変わり、ある日ふとした瞬間に、チョウゲンボウの行動に変化が見られることもあります。
その小さな変化を喜びながら、共に歩む時間を大切にしましょう。
なつく個体・なつかない個体の違いとは?
性格や育った環境によって、なつきやすさは大きく異なります。
特に野生に近い環境で育った個体は、警戒心が強い傾向があります。
また、幼鳥のころから人と接している個体は比較的なつきやすく、人の存在を安心できるものと認識しやすいです。
逆に、過去に怖い思いをしたことがある個体や、元々用心深い性格の個体は、人に慣れるまでにかなりの時間を要することもあります。
なつく・なつかないを決めつけるのではなく、その子のペースに寄り添いながら信頼関係を築いていく姿勢が大切です。
チョウゲンボウとの暮らしで後悔しないために
しっかりと準備し、理解を深めた上で迎えることが、チョウゲンボウとの豊かな暮らしへの第一歩です。
必要な設備や法律面の確認、専門的な知識の習得はもちろん、日々のケアにかかる時間や労力についても把握しておきましょう。
また、なつくまでには個体差があることや、思い通りにいかないこともあるという心構えも重要です。
知識と愛情をもって接すれば、時間と共に強い信頼が生まれ、チョウゲンボウはかけがえのない存在となるでしょう。
日々の小さな変化や反応を大切にしながら、絆を深めていく過程そのものが、チョウゲンボウとの暮らしの魅力なのです。
チョウゲンボウはなつくのか? まとめ
- チョウゲンボウは小型の猛禽類で、比較的おとなしく飼育しやすい
- 野生下より飼育下の方が長生きする傾向がある(最大15年程度)
- 性格や育った環境によって、なつく度合いに個体差がある
- 幼鳥期から育てることで、なつきやすくなる
- 静かで安心できる環境と広いスペースが必要
- 毎日の手渡しエサやりや声かけで信頼関係を築く
- ご褒美を使ったポジティブな訓練が効果的
- なつきすぎると依存が強くなり、逆にストレスを感じることもある
- なつかない場合も、環境や接し方を工夫することで改善が可能
- 法的な許可や専門知識が必要なため、事前の準備が大切
- 長期的な覚悟と愛情があれば、かけがえのない存在に育つ
関連記事はこちらから!!
ハリスホークはうるさい?うるさくなる理由と知っておくべき対処法




















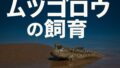
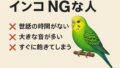
コメント