「ワタリガニって飼えるの?」
「海で見かけたけど、自宅でも育てられるの?」
「飼育が難しいって聞いたけど、実際はどうなの?」

そんな疑問を持っている方に向けて、本記事ではワタリガニの飼育のリアルについて徹底解説します。
観賞用としての魅力はもちろん、飼うために必要な準備、注意すべきポイント、地域によっては飼育や採取が制限される可能性についても触れています。
飼育を始める前に、ワタリガニという生き物をきちんと理解し、後悔のないよう正しい知識を身につけましょう。
✔ ワタリガニの飼育は可能
✔ 淡水魚よりも設備や水質管理がシビア
✔ 地域によっては飼育や採取が禁止されていることもある
✔ 正しい環境を整えれば、健康的に長生きさせることができる
ワタリガニの飼育について

・ワタリガニの飼育は禁止されているのか?
・ワタリガニの寿命
・ワタリガニの成長速度
・ワタリガニの餌
・ワタリガニってなつく?
・ワタリガニは混泳できる?
・ワタリガニの飼育に必要な準備
・ワタリガニ飼育に向いている人・向いていない人
・ワタリガニに適した水温・塩分濃度の管理方法
・ワタリガニ飼育にかかる費用の目安
ワタリガニってどんなカニ?
ワタリガニは、日本各地の沿岸部に生息するカニの一種で、強靭な脚力を活かして海底をすばやく移動する姿が特徴的な生き物です。
その動きは俊敏で、外敵から身を守る能力にも優れています。
攻撃的な性格を持つ一方で、非常に警戒心も強く、水中では岩陰や砂の中に隠れることもよく見られます。
ワタリガニは日本では食用としても非常に人気が高く、旬の時期には市場でもよく見かける存在です。
味が濃く、みそや身の風味が強いため、料理でも重宝されています。
その一方で、ユニークな生態と活発な動き、そして見た目の美しさから、観賞用として飼育を楽しむ人も増えてきています。
特に水中での動きや脱皮の様子は観察しがいがあり、水槽内の主役としても魅力的な存在です。
水槽をレイアウトして自然に近い環境を再現することで、より豊かな行動を見せてくれる点も、飼育の楽しみのひとつといえるでしょう。
さらに、個体ごとに行動パターンや好む隠れ場所が異なるため、見ていて飽きないという声も多く聞かれます。
魚と一緒に飼育は難しいですが、ワタリガニは飼育し易くオススメ出来ます。脱皮を繰り返して30cmくらいまで成長しますし、好き嫌いなく色々食べます。
【見所】不器用な食事風景。人に懐かぬワイルドさ。
ハサミの回避方法は全力で拳を握る。ハサミが筋肉で滑り、薄皮剥ける程度で済みます。 pic.twitter.com/Cd4Bdad5LV
— 黎明卿もがらーあべ (@siotonkotsumiso) June 16, 2019
ワタリガニの飼育は禁止されているのか?
ワタリガニの飼育自体は、日本国内で一般的に禁止されていません。
しかし、採取方法や地域によっては規制が存在するため、注意が必要です。
採取方法の規制:
例えば、愛知県では「愛知県漁業調整規則第42条」により、ライトを使用したたも網やカニ網を用いたカニ類の採取が禁止されています。
これは、資源保護や漁業秩序の維持を目的とした措置です。
地域ごとの規制: 他の地域でも、漁業調整規則や委員会指示により、特定の漁具や採取方法が制限されている場合があります。
また、特定の水域では漁業権が設定されており、無許可での採取が禁止されていることもあります。
飼育を始める前に、地元の漁業協同組合や自治体の水産課などに問い合わせ、最新の情報を確認することをおすすめします。
ワタリガニの寿命は?
ワタリガニの寿命は一般的に2〜3年ほどとされていますが、飼育環境が整っており、適切な水質や温度、栄養管理が行われていれば、それ以上生きることも十分に可能です。
とくに人工海水の塩分濃度の管理や、日常的な水換え、安定した餌の供給ができていると、より長く健康を保つ傾向があります。
また、脱皮のタイミングやその前後のケアも寿命を延ばす鍵となるため、日々の観察が重要になります。
長期飼育を目指すのであれば、季節ごとの環境調整やストレスの少ない飼育スタイルを心がけましょう。
ワタリガニの成長速度

ワタリガニの成長は比較的早く、飼育開始から数ヶ月のうちに明らかにサイズの変化が見られるほどです。
成長の過程では定期的に脱皮を繰り返し、そのたびに一回り大きくなります。
特に、成長期には週単位で脱皮が発生することもあり、脱皮のたびに殻の質感や体色に変化が見られることもあります。
適切な餌(タンパク質を含むもの)を与え、水温を20〜25℃に保つことで成長を促進することができます。
脱皮直後の個体はとてもデリケートな状態になるため、他の生物と接触させず、静かな環境で保護することが望ましいです。
こうした成長プロセスを間近で観察できるのは、ワタリガニ飼育の醍醐味の一つです。
ワタリガニの餌
ワタリガニは主に魚介類を好む雑食性の甲殻類であり、自然界では小魚、貝類、ゴカイ、エビなどを捕食しています。
飼育下でもこれに近い食生活を再現することが望ましく、市販の冷凍シーフード(アサリ、エビ、イカなど)を小さくカットして与えると喜びます。
また、専用の甲殻類用フードや沈下性ペレットも栄養バランスを補う目的で有効です。
与える回数は1日1回が基本ですが、成長期や脱皮前など活動が活発な時期には少し多めに与えても問題ありません。
ただし、食べ残しが水質悪化の原因になるため、与える量には注意が必要です。
食べ残した餌はすぐに取り除くようにしましょう。
ワタリガニってなつく?
基本的にはワタリガニは人に懐くようなペットではありません。
犬や猫のように触れ合いを求めることはなく、警戒心が強いため手を近づけると逃げたり威嚇したりすることがあります。
しかし、毎日決まった時間に餌を与えることで「餌=人間」という認識が生まれ、餌やりのタイミングで近寄ってくる個体もいます。
こうした反応を楽しむことはできますが、過度な期待は禁物です。
無理な接触や刺激はストレスになるため、静かに見守るスタンスが大切です。
ワタリガニは混泳できる?

ワタリガニは非常に縄張り意識が強く、攻撃的な性格を持っているため、基本的には単独飼育が強く推奨されます。
特に同種や他の甲殻類、底棲性の魚との混泳はケンカや共食いの原因となり、最悪の場合は命を落とすこともあります。
どうしても混泳させたい場合は、水槽を広くし、隠れ家やシェルターを複数設置するなど、視界を遮る工夫が必要です。
ただし、これでも争いを完全に防ぐことは難しいため、混泳は基本的に避けるのが無難です。
ワタリガニの飼育に必要な準備
ワタリガニを健康的に飼育するためには、ある程度本格的な設備が求められます。
まず、水槽は最低でも60cm以上の広さが必要で、成長に合わせて90cm程度のものが望ましいでしょう。
活発に動き回る性質があるため、十分なスペースを確保してやることが重要です。
脱走防止のために、しっかりと閉まるフタも必須アイテムです。
ワタリガニは脚力が非常に強く、わずかな隙間からでも脱走することがあります。
重みのあるフタやロック機能があるものを選ぶとより安心です。
また、水温を一定に保つためのヒーターや、排泄物や食べ残しからくる水質悪化を防ぐためのフィルターも必需品です。
エアレーションを使用することで水中の酸素濃度を保ち、ワタリガニの健康維持につながります。
60cmの水槽に、ヒーター、照明、フィルターが全てついているので、これ一つで飼育の準備がほとんどできてしまいます。
値段もなんと1万円を切っているので、かなりお得な水槽だと思います!
塩分濃度の管理は非常に重要で、安定した環境づくりに欠かせません。
これらを総合的に整えることで、海水魚と同じように安定した飼育が可能になります。

ワタリガニ飼育に向いている人・向いていない人
ワタリガニの飼育には、日々の観察力と環境管理の継続が求められるため、動物の行動をじっくり見るのが好きで、水質や設備の状態をこまめにチェックできる人に向いています。
飼育者の注意深さが健康維持に直結するため、自然や生き物に関心がある人には特におすすめです。
一方で、ペットとの触れ合いを重視する人や、定期的な掃除・水換えといった管理作業に手間を感じる人には向いていません。
また、見た目に癒しを求めるだけで飼い始めると、思った以上の管理の手間にギャップを感じてしまうこともあるので注意が必要です。
ワタリガニに適した水温・塩分濃度の管理方法

ワタリガニにとって快適な環境を維持するには、水温と塩分濃度の管理が非常に重要です。
理想的な水温は20〜25℃で、急激な温度変化はストレスや病気の原因となるため、季節や室温に応じてヒーターや冷却ファンを使って調整しましょう。
塩分濃度については、比重1.020〜1.025程度が適切とされており、人工海水の素と比重計を使って正確に調整することが必要です。
水質の安定を保つためにも、週に1回を目安に全体の1/3程度の水換えを行い、濾過装置のメンテナンスも定期的に行うとより良い環境が維持できます。
ワタリガニ飼育にかかる費用の目安
ワタリガニを飼育する際の費用は、初期費用とランニングコストに分かれます。
初期費用としては、水槽(60cm以上)、ヒーター、フィルター、エアレーション装置、人工海水の素、比重計、照明などの機材一式でおおよそ1万円〜2万円程度が目安です。
設備のグレードやデザインにこだわる場合、さらに費用がかかることもあります。
また、ランニングコストとしては、人工海水用の塩や水道代、電気代(ヒーター・フィルター・エアレーション)、餌代などを含めて月あたり1,000円〜3,000円程度です。
さらに、水換えに使うカルキ抜きや掃除用の道具も定期的に交換が必要なため、それらを含めるとやや高めに見積もっておくと安心です。
ワタリガニは海水環境の維持が重要なため、淡水魚よりもややコストがかかりますが、きちんと準備すれば長く健康に育てることができます。
ワタリガニの飼育のコツ

・脱皮時のケアと失敗を防ぐポイント
・弱りのサインを見逃さないために
・水換えと掃除の頻度と方法
・冬の水温管理と加温対策
・長期間の不在時はどうする?
・ワタリガニの飼育 まとめ
飼育中に起きやすいトラブルとその対処法
水質悪化や脱皮失敗、共食いなどが主なトラブルとして挙げられます。
特にワタリガニはデリケートな面があり、少しの水質の乱れや環境の変化が大きなストレスとなり、体調を崩す原因になります。
アンモニアや亜硝酸の濃度が高くなると、呼吸困難や動きの鈍化といった症状が出やすいため、水質の定期的なチェックは不可欠です。
また、共食いも意外と多いトラブルの一つです。
とくに脱皮直後など体が柔らかい時期は他個体から襲われやすいため、やはり単独飼育がもっとも安全といえるでしょう。
どうしても複数飼いたい場合は、隔離スペースを設ける、シェルターを多く配置するなどの対策が求められます。
トラブルを未然に防ぐためには、日々の観察と飼育環境の安定がカギとなります。
脱皮時のケアと失敗を防ぐポイント
脱皮はワタリガニの成長に欠かせない重要なプロセスですが、同時に最もリスクの高いタイミングでもあります。
脱皮前には落ち着きがなくなったり、餌を食べなくなったりする兆候が見られることがあります。
こうしたサインを見逃さずに、周囲の環境を静かに保ち、ストレスのかからない状態で脱皮を迎えさせてあげましょう。
脱皮後の殻はすぐに取り除かず、水槽内に数日残しておくことで、ワタリガニが自らの殻を食べてカルシウムを補給することができます。
また、脱皮直後は身体が非常に柔らかいため、他の生き物と接触させないようにするのも重要です。
もし複数飼育をしている場合は、脱皮個体を隔離して保護する環境を整えましょう。
半年飼育してるワタリガニが脱皮してえらいでかくなった…。
全長18cmでかっ!?
左にあるのが抜け殻。 pic.twitter.com/YLPqoQ2on9— カムシン@スタミナ強化中💪 (@carom_come) November 18, 2022
弱りのサインを見逃さないために

ワタリガニが病気になったり、体調を崩したりする際にはいくつかのわかりやすい兆候があります。
最も一般的なのは食欲不振で、いつもならすぐに食べる餌を見向きもしない状態が続いた場合は注意が必要です。
また、活動が極端に少なくなる、底でじっとして動かない、あるいは泳ぎ方が不自然であるといった様子も、弱りのサインと考えられます。
さらに、脚が取れている、殻が変色している、体表に異常な斑点や白っぽい膜がある場合は、細菌や寄生虫の可能性もあります。
これらのサインを見逃さずに、早めに水質のチェックを行い、塩分濃度やアンモニア値、pH値などに異常がないか確認することが大切です。
状態が悪化する前に、別の隔離水槽で様子を見たり、必要に応じて水換えや温度調整などの対処をしましょう。
水換えと掃除の頻度と方法
ワタリガニの健康を保つためには、定期的な水換えと掃除が欠かせません。
基本的には週に1回、全体の水量の1/3程度を目安に新しい人工海水に交換します。
水換えの際には、底砂に溜まった汚れをプロホースなどで吸い出すと効果的です。
フィルターの清掃も重要で、月に1回は濾材を軽くすすぎ、フィルター内にゴミや汚れが溜まっていないかチェックしましょう。
ただし、バクテリアのバランスを崩さないよう、すすぎすぎには注意が必要です。
日常的には、餌の食べ残しやフンを見つけたら早めに取り除くことで、水質悪化を防ぐことができます。
冬の水温管理と加温対策

寒い季節には水温の低下がワタリガニにとって大きなストレスとなります。
ワタリガニに適した水温は20℃〜25℃で、特に冬場は20℃を下回らないようにすることが重要です。
水槽用のヒーターを使用し、水温計で常に温度を確認できる状態にしておきましょう。
また、夜間の冷え込み対策としては保温マットや断熱材を使うのも効果的です。
水槽を部屋の隅や日当たりの良い場所に置くことで、急激な温度変化を防ぐ工夫も有効です。
もし外気温が極端に低い地域にお住まいの場合は、サーモスタット付きヒーターを選ぶとより安全で安定した環境が維持できます。
長期間の不在時はどうする?
ワタリガニの飼育中に数日以上家を空ける場合、事前の準備がとても重要になります。
まず最も一般的な対策は、自動給餌機を導入することです。
一定の時間に決まった量の餌を与えることができるため、短期間であれば十分に対応可能です。
ただし、使用前に必ず動作確認をして、正しく餌が出るか、湿気などで詰まらないかを確認しておきましょう。
また、より安心できる方法としては、信頼できる家族や友人に世話をお願いするのが理想的です。
簡単な餌やりの方法や、機器のチェックポイント、水槽の様子を観察するポイントなどをメモにして伝えておくとスムーズです。
旅行前には水換えを済ませ、フィルターやエアレーション機器などの動作を確認し、異常がないかをチェックしておきましょう。
また、停電や故障のリスクを考慮して、予備の機器を用意しておくのもおすすめです。
長期旅行の場合は、脱皮やトラブルの可能性もあるため、なるべく信頼できる人に細かく管理してもらう方が安心です。
ワタリガニの飼育 まとめ

ワタリガニは美しく観察しがいのある生き物ですが、飼育には手間と注意が必要です。
正しい知識と設備を整えれば、長く健康に育てることができます。
ぜひこの記事を参考に、楽しいワタリガニライフを始めてみてください!
関連記事はこちらから!!






















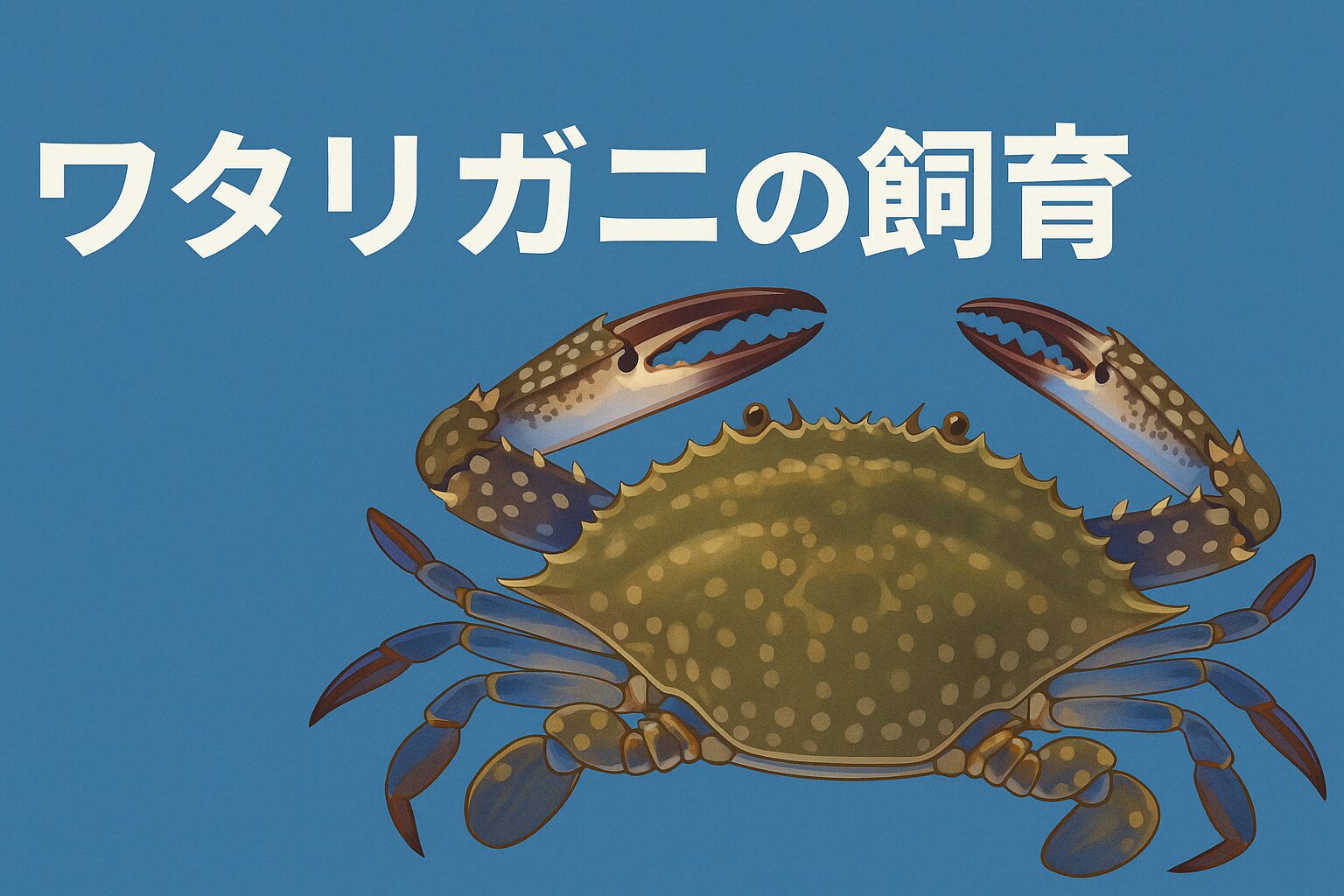

コメント