「ファンシーラットって人に懐くって聞いたのに、急に噛まれてびっくりした…」
「可愛いけど、実はよく噛むって本当?」
「本気噛みしてくるの?」

そんな疑問を持っている方に向けて、本記事ではファンシーラットがなぜ噛むのか?という原因や背景から、噛み癖の見分け方、正しい対応方法、そして信頼関係の築き方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
「ファンシーラットは噛む生き物なのか?」その答えと向き合い方を知ることで、もっと安心してお世話ができるようになります。
✔ 噛む理由は「恐怖」「不安」「環境ストレス」などが多い
✔ 甘噛みと本気噛みの違いを見極めることが大切
✔ 正しい接し方と環境づくりで噛み癖は改善できる
ファンシーラットは噛むのか?

・甘噛みと本気噛み
・ファンシーラットの威嚇
・噛むのは「恐怖」や「不安」のサインかも
・成長期や発情期に見られる噛み行動
・飼育環境や接し方によっても変わる
「ファンシーラットって懐くって聞いたのに、なんで噛むの?」
そんな疑問や不安を抱えている飼い主さん、多いのではないでしょうか?
実は、ファンシーラットが噛むのにはちゃんとした理由があります。
そして、その多くは私たち人間の行動や環境が影響していることも。
ここでは、ラットの性格や行動の背景をしっかり知り、「なぜ噛むのか?」「どうすれば改善できるのか?」を深掘りしていきましょう。
ファンシーラットの性格

ファンシーラットは非常に賢く、社交的で人懐っこい動物です。
名前の通り、実験動物とは違い、ペット用に繁殖された品種で、人間との生活に向いている個体が多いのが特徴です。
人間の声やにおいにすぐに反応する子も多く、慣れてくれば飼い主の手を舐めたり、後ろをついてくるような行動も見せます。
とはいえ、性格は個体差が非常に大きく、すべてのラットが最初からフレンドリーというわけではありません。
初対面の人に対しては慎重だったり、物音に敏感でビビりな子もいます。
特に、すでに大人のラットや多頭飼育から迎え入れた場合、以前の環境によっては人間に対して警戒心を持っていることもあります。
また、臆病な性格の子は、見慣れない手や急な動きに対して防衛本能が働き、噛んでしまうことがあるのです。
そのため、ファンシーラットと良好な関係を築くには、まずラットが安心できる環境を整えることが第一歩です。
慣れていないうちは無理に触ろうとせず、ゆっくりと時間をかけて信頼を育てる姿勢が大切になります。
甘噛みと本気噛みの違い
ラットの噛む行動には甘噛みと本気噛みがあります。
甘噛みは、「興味がある」「遊んでほしい」といった軽いスキンシップの一環で、ほとんど痛みはありません。
ときには、毛づくろいの延長のように軽く歯を当ててくることもあります。
これは、ラットなりの愛情表現だったり、「あなたに注目してほしい」という気持ちの表れでもあります。
少し休憩~🍵
待機中のファンシーラット🐭
個人的にこの左手が可愛くていい✨
可愛いとは言ってもケージの外から手を近づけたら噛まれるんだけどね💦ネズミ系はたまにそういう噛む癖のある子達がいるから、お迎えした最初の頃は気をつけてね。 pic.twitter.com/GFwxsKUThr
— 松本祐治(ブリーダーショップ空 店長) (@bs_kuu0726) July 23, 2022
一方で本気噛みは、「怖い」「嫌だ」という強い感情が表れた防御的な行動です。
強く噛まれた場合は、ラットが強いストレスを感じていたり、驚かされたことが原因であることが多いです。
また、寝ているときに突然触られたり、餌を取られたと勘違いした場合など、予期せぬ状況に反応してしまうこともあります。
本気で噛まれたときの痛みは、かなり痛いです。
もちろん血も出ます。
特に皮膚が薄い指先や手の甲などは傷つきやすく、噛まれた箇所が赤く腫れたり、ミミズ腫れのようになることもあります。
ラットの前歯は非常に鋭く、かじるために発達しているため、見た目以上にダメージを受けることもあるのです。
そのため、本気噛みの兆候にいち早く気づき、未然に防ぐ行動を心がけることがとても重要です。
甘噛みと本気噛みの違いを理解することで、ラットの気持ちをより的確に読み取れるようになります。
行動の背景を観察し、その時の状況やラットの表情・しぐさも含めて判断してあげることが大切です。
ファンシーラットの威嚇
ファンシーラットが噛む前には、さまざまな「威嚇行動」を見せることがあります。
これらのサインを見逃さずに観察することで、噛まれるリスクを減らし、ラットの気持ちを理解する助けになります。
代表的な威嚇行動には以下のようなものがあります:
・体を固くして動かなくなる
・「シャー」という鳴き声を出す
・しっぽをバタバタさせる、振る
・背中の毛が逆立つ
・じっと見つめたまま動かない
こうした威嚇サインが見られたら、無理に触ろうとせず、ラットが落ち着くまで距離を取りましょう。
威嚇の理由は環境の変化や体調不良、または飼い主との関係性に起因していることがあるため、焦らず丁寧に接することが大切です。
ラットにとって「威嚇=本気で嫌がっている」状態です。
逆に言えば、威嚇しているうちに気づいて対処すれば、本気噛みまで至るリスクは大きく下げられます。
噛むのは「恐怖」や「不安」のサインかも

「可愛いからつい触りたくなっちゃう」
その気持ち、すごく分かります。
でも、ラットからすると「いきなり何!?」とビックリしてしまうこともあります。
特に、まだ飼い主の存在に慣れていないラットに対して、急に手を伸ばしたり、掴んだりすると、ラットは驚きと恐怖を感じてしまいます。
寝ているところを起こされたり、無理に体を持ち上げられた場合なども同様で、これらはラットにとってストレスフルな体験です。
その結果として、「怖い!」「これ以上やめて!」という気持ちを伝える手段として噛むことがあります。
このような噛む行動は、攻撃的な性格や反抗心の表れではなく、あくまで防衛反応です。
ラットは自分の身を守るために噛んでいるのであり、飼い主を傷つけようとしているわけではありません。
むしろ、「これ以上踏み込まないで」という心の叫びでもあるのです。
また、恐怖や不安を感じる原因は、飼い主の行動だけではなく、周囲の環境にもあります。
大きな音や突然の振動、慣れないにおい、光の刺激など、些細なことでもラットは敏感に反応します。
こうした環境要因が積み重なると、ラットのストレスが蓄積し、それが噛みつきという行動に現れることがあります。
だからこそ、ラットが「何に対して不安を感じているのか?」を日頃から観察し、恐怖の原因を一つずつ取り除いていく姿勢が大切です。
安心して過ごせる空間と、穏やかな飼い主の存在こそが、ラットの噛み癖を減らす第一歩になります。
成長期や発情期に見られる噛み行動
生後2〜4ヶ月のいわゆる成長期には、ラットの性格や行動に大きな変化が見られることがあります。
この時期、ホルモンバランスが急激に変化し、それに伴ってイライラしやすくなったり、気が荒くなったりすることがあります。ちょうど人間の思春期のような状態です。
また、発情期になると、特にオスのラットは縄張り意識が強くなり、同じ空間にいる人間や他の動物に対して攻撃的な態度を取ることもあります。
普段は大人しい子でも、この時期だけは突然噛みつくような行動を見せることがあります。
こうした行動は一時的なものであり、多くの場合、時期が過ぎれば落ち着いてきます。
無理に抑え込もうとしたり、怒ったりするとかえって逆効果になることもあるため、この時期はラットとの距離感を大切にしながら、静かに見守る姿勢が求められます。
加えて、成長期には好奇心が旺盛になるため、何でも噛んで確かめようとする傾向も強くなります。
人間の手や服、アクセサリーなどに興味を持って噛みつくこともあるので、ラットにとって安全な噛みおもちゃなどを用意して、ストレス発散と好奇心の両方を満たしてあげるとよいでしょう。
飼育環境や接し方によっても変わる
ラットが噛む原因は、実は環境的な要因によるものが非常に多いです。
たとえば、ケージが狭すぎて十分に体を動かせない、隠れ家がなくて常にオープンな空間で落ち着かない、水や餌が不十分で基本的なニーズが満たされていないといったケースが挙げられます。
また、周囲の騒音や強すぎる照明、人の気配が絶え間なくあるような落ち着かない環境では、ラットのストレスはどんどん蓄積していきます。
ラットは夜行性のため、日中に静かで暗めの空間があることも重要なポイントです。
ストレスが慢性化すると、常に神経質になり、わずかな刺激にも過敏に反応してしまい、結果として噛む行動につながることがあります。
飼い主側の接し方も、ラットの安心感に大きく影響します。
たとえば、いきなり上から手を入れて掴もうとしたり、大きな声で話しかけたりすることは、ラットにとって「捕食者の動き」に見えてしまい、本能的な恐怖を誘発してしまいます。
特に、まだ人に慣れていないラットに対しては、目線を低くしてゆっくりと近づき、手の匂いを嗅がせるなど、穏やかなアプローチが必要です。
また、定期的な掃除やケージのレイアウト変更など、環境に変化を加える際も注意が必要です。
急な変化は不安のもとになり、せっかく築いた信頼関係にヒビが入ることもあります。
ラットが安心して過ごせるルーティンを守りつつ、ゆるやかに改善・調整していくことが大切です。
つまり、「安心できる環境+穏やかな接し方」が、噛み癖予防の基本であり、信頼関係を深めるための土台になるのです。
ファンシーラットが噛むのをやめさせるには

・手は怖くないものだと理解させる
・人間に慣れさせる
・おやつを使った信頼関係の築き方
・ケージの環境を見直してストレス軽減
・継続的なふれあいで噛み癖は改善できる
・ファンシーラットは噛むのか? まとめ
噛まれたときに取るべき正しいリアクション
では、もしファンシーラットが噛むようになってしまったら、どう対応すればよいのでしょうか?
うまく対応できずに、ずっと噛み癖が治らないと飼って後悔する可能性も出てきます。

ここでは、実際にできるしつけや環境改善の方法を紹介します。

まずやってはいけないのは、「叩く」「怒鳴る」「驚かせる」などのネガティブな反応。
これは逆効果で、ラットにとってはトラウマになります。
ラットはとても繊細な動物で、強い刺激に対して強烈な記憶を残します。
一度でも怖い思いをすると、飼い主の手に対して不信感を持ってしまい、関係の修復に長い時間がかかることも。
噛まれたときには、「痛いけど冷静に手を引く」ことが何よりも大切です。
決してリアクションを大げさに取らず、あえて無表情で静かに距離を取ることで、ラットに「噛んでもいいことは起きない」ということを学ばせることができます。
言葉は通じなくても、態度から伝わるメッセージはとても大きいのです。
また、噛まれたあとに距離を取り、「ダメだよ」などと一言伝えるのも効果的です。
大切なのは、叱るのではなく、冷静に意思表示するという点。
怒鳴らなくても、ラットには飼い主の感情はしっかり伝わります。
手は怖くないものだと理解させる

手を怖がるラットには、まず「手=安心できるもの」というイメージを持たせることが大切です。
ラットにとって手という存在は巨大で、急に現れると驚いてしまいます。
信頼関係を築くためには、日々の積み重ねが必要です。
・ケージに手を入れるだけで何もしない日を作る
・おやつを手に乗せて差し出すことで、手の存在をポジティブに認識させる
・手のひらをじっと置いたままにし、においを嗅がせるだけの時間をとる
こうした小さな行動の繰り返しで、ラットは次第に「手=怖くない」「良いことがある存在」と学習していきます。
初めは緊張していても、回数を重ねることでだんだんとリラックスした様子を見せてくれるようになるでしょう。
ラットのペースに合わせて進めることが最も大切です。
一日でも早く仲良くなりたいという気持ちは分かりますが、焦らず、じっくり信頼を育てていくことが、噛み癖を直す第一歩になります。
人間に慣れさせる

日常的なスキンシップは、ラットの社会性を高め、人に慣れるきっかけになります。
ラットは非常に知能が高く、個体ごとに性格や感情表現が異なるため、じっくり時間をかけて心を開いていくことが大切です。
まずは短時間のふれあいから始めて、徐々にその時間を延ばしていきましょう。
たとえば、最初はケージの外に出た状態で手のひらの上に乗せてみる、飼い主の膝の上でじっとさせてみる、軽く撫でてみるなど、ラットが嫌がらない範囲で試してみることがポイントです。
また、名前を呼んでからおやつを渡す、声をかけながら優しく触れるなど、ラットが「この人は自分にとって安全で、良いことをしてくれる存在だ」と認識できるような行動を繰り返すことが大切です。
こうした日々のルーティンを通して、ラットは飼い主の声や匂い、触れ方に慣れていき、次第に不安や警戒心を解いてくれるようになります。
特に信頼関係の構築においては、ラットのペースに合わせることが最重要です。
すぐに抱っこさせてくれなくても焦らず、ラットが自分から近づいてくるまで待つことが成功の鍵です。
人間と同じように、信頼は一朝一夕では築けませんが、時間をかけることで深く確かな関係が生まれます。
おやつを使った信頼関係の築き方
おやつはラットとの距離を縮めるための強力なツールです。
ただし、単に与えるのではなく、関係づくりの一環として計画的に活用することがポイントです。
手のひらにおやつを乗せて、ラットが近づいてきたときに与えることで、「この人に近づくと良いことがある」とラットに学習させることができます。
これを繰り返すことで、ラットは手に対する恐怖心を徐々に失い、積極的にコミュニケーションを取ろうとするようになります。
与えるおやつは、ヒマワリの種やリンゴの小片、イチゴ、とうもろこしの粒など、ラットが好きで食べやすいものを選びましょう。
においが強いものほど、初期段階では効果的です。
ただし、カロリーが高すぎたり、糖分の多いものは与えすぎに注意し、1日数回の特別なご褒美として使うのがおすすめです。
私のおすすめはこのひまわりの種です。
おやつのタイミングも重要で、ふれあいのあとやラットが落ち着いているタイミングで与えると、ポジティブな印象をより強く与えることができます。
こうして少しずつ、ラットにとっての“安心できる人”という存在になっていきましょう。
ケージの環境を見直してストレス軽減

もし噛み癖がひどくなったと感じたら、まずはラットの住環境をしっかりと観察してみましょう。
ラットにとって、安心できる空間は心の安定に直結します。
環境が整っていないと、それだけで常に警戒心を持ち、噛み癖や攻撃的な行動につながることがあります。
・静かな場所にケージを設置しているか?
・隠れ家や回し車、おもちゃなどの遊び場はあるか?
・温度や湿度は適切か?
・ケージの清潔さは保たれているか?
加えて、昼夜のリズムを意識した照明の工夫や、静かに過ごせる時間帯の確保も、落ち着いた性格づくりには効果的です。
ラットが安心して眠れる、落ち着いて過ごせる場所を提供することは、噛み癖予防・改善に大きく関係しています。
快適な住環境というのは単に清潔さや設備の充実だけではなく、ラットの習性や性格に合った空間づくりをすることです。
彼らがここは自分のテリトリーだと感じ、くつろげるようになれば、噛む必要性すら感じなくなるでしょう。
継続的なふれあいで噛み癖は改善できる
ラットは賢く、感情をしっかりと持った動物です。
そのため、時間をかけて向き合うことで、少しずつ信頼を深めていくことができます。
一度心を開いてくれると、まるで犬や猫のように懐いてくれることも珍しくありません。
継続的なふれあいは、ラットにとって「この人は安全」「この人と一緒にいると楽しい」と学ぶ機会になります。
たとえば、毎日同じ時間に声をかけたり、手からおやつを与えたり、膝の上で静かに過ごす時間を作るなど、ルーティン化することで安心感を高めることができます。
最初は数分からで構いません。
ラットの表情や反応を観察しながら、嫌がっていないか、リラックスしているかを見極めてください。
そして、信頼が積み重なるにつれて、自然と噛む行動が減っていきます。
「この人は安心できる」と思ってもらえるよう、日々の小さな積み重ねを大切にしていきましょう。
噛み癖も一時的なものであることが多く、信頼関係が築かれることで自然と改善していきます。
焦らず、気長に取り組む姿勢が何よりの近道です。
ファンシーラットは噛むのか? まとめ
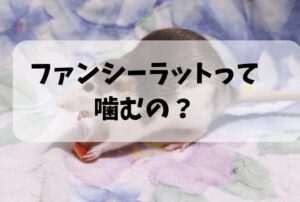
ファンシーラットが噛む理由はさまざまですが、その多くは「防衛反応」や「環境・関係性の問題」に起因しています。
たとえば、急な接触や慣れていない環境に置かれると、ラットは身の危険を感じて反射的に噛むことがあります。
これは攻撃ではなく「身を守るための手段」であり、決して性格が悪いとか、人間に懐かないという意味ではありません。
むしろ、噛むという行動は「もっと自分の気持ちを分かってほしい」「怖い思いをしているんだよ」というラットからのサインかもしれません。
そう考えると、噛まれた経験もラットとの信頼関係を深めるためのひとつのきっかけになります。
ファンシーラットは飼ってから後悔するのが多いペットとしても知られています。
ファンシーラットを飼うと後悔する理由とは?飼う前に知るべき10のこと
飼い主として大切なのは、恐怖や不安の要因を少しずつ減らし、日々のふれあいの中で信頼を育てていく努力を惜しまないことです。
優しく声をかけたり、穏やかな態度で接したり、小さな積み重ねがラットに安心感を与えます。
時間をかけて丁寧に向き合えば、ファンシーラットは必ずその気持ちに応えてくれます。
そして、ただのペットではなく、心通じ合う最高のパートナーになってくれるはずです。

ラット系の関連記事はこちらから!!
「パンダマウスって共食いするの?」初心者が知っておくべき注意点と防ぐ方法
ステップレミングはなつくのか?臭い?飼育前に必ず知っておくべきこと10選!



















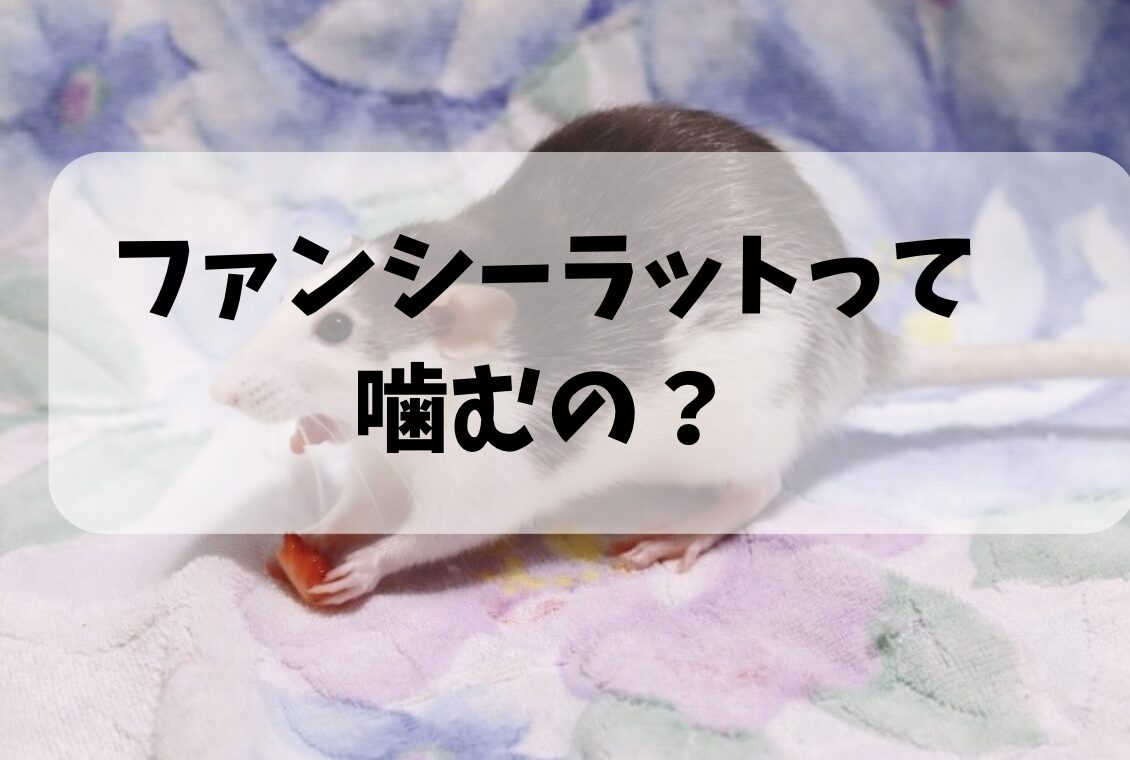


コメント