「ファンシーラットって見た目は可愛いけど、実は臭いって本当?」
「飼ってみたいけど、部屋にニオイがこもったりしないか不安…」
「清潔にしてるつもりなのに、なぜかケージ周辺が臭う気がする…」

そんな疑問やお悩みを持っている方に向けて、本記事ではファンシーラットの『臭い問題』について徹底的に解説します。
SNSや口コミで「ラットは臭い」という声がある一方で、「ぜんぜん臭くないよ!」という声もあり、何を信じたらいいかわからなくなることもあるかもしれません。
この記事では、ファンシーラットの臭いの正体や原因を明らかにしつつ、臭いを抑えるために知っておくべき飼育ポイントや具体的な対策も紹介します。
「ファンシーラットって本当に臭いのか?」 その答えを明らかにし、においの悩みを解消して、もっと快適にラットと暮らすヒントをお届けします!
✔ ファンシーラット自体はそこまで臭う動物ではない(臭いの原因は他にある)
✔ ニオイの原因は排泄物や巣材、通気性など環境にあり
✔ トイレのしつけや掃除習慣でニオイ対策は十分に可能
✔ 正しい知識と環境づくりで、快適なラットライフを楽しもう
ファンシーラットって臭い?

・オスとメスで臭いに違いはある?
・ニオイの原因① 尿やフンによる臭い
・ニオイの原因② 巣材や床材の汚れ
・ニオイの原因③ ケージの通気性が悪い
・ニオイの原因④ 食べ残しの腐敗臭
ファンシーラットは本当に臭いのか?
「ファンシーラットって、見た目は可愛いけど…臭いって聞いたことがある」と心配になる方も多いのではないでしょうか?
実際、SNSや掲示板などで「ファンシーラット=臭い」というイメージが広まっており、それが気になって飼育をためらう人もいます。
しかし、ファンシーラット自体はそこまで強烈なニオイを発する動物ではありません。
犬や猫と同様、基本的には清潔好きで、自分で毛づくろいもよく行います。
特に、掃除を怠ったり、換気が不十分だったり、食べ残しが放置されている場合などには、においが強くなる傾向があります。
そのため、「ファンシーラットが臭いのかどうか」は、実は飼い主側の管理に大きく左右される問題なのです。
ファンシーラット可愛すぎる(臭いは殺人級) pic.twitter.com/LR8GGtLPoO
— 鶏ガラ (@BloodPytho) May 16, 2015
オスとメスで臭いに違いはある?
実際、オスの方がメスよりも体臭が強い傾向があります。
これは、オスの方が縄張り意識が強く、匂いづけのために皮脂腺からの分泌が多くなるからです。
皮脂腺から出る分泌物は、ケージの壁やアイテムにこすりつけてマーキングされることがあり、これが臭いの一因になります。
特に去勢していないオスは、においが強くなる傾向があります。
性ホルモンの影響でマーキング行動が活発になるからです。
一方、メスは比較的さっぱりとした体臭で、掃除をしっかりしていればほとんど気になりません。
また、メスは清潔好きな個体も多く、食べ物を隠すことも少ないため、ケージ内も清潔に保ちやすい傾向があります。
ニオイの主な原因①|尿やフンによる臭い

もっともよくある原因が、尿とフンの放置によるアンモニア臭です。
特にラットは排泄の頻度が高く、小さな体でも毎日たくさんの尿とフンを出します。
放置された排泄物はすぐに分解されてアンモニアを発し、強い刺激臭となってケージ内に充満します。
ラットはとてもトイレを覚えやすい動物として知られていますが、すべての個体が必ず覚えるわけではなく、特に飼い始めの時期にはケージ全体で排泄してしまうこともあります。
そのため、こまめな掃除を怠ると、すぐに強烈な臭いが広がってしまいます。
また、トイレの場所をある程度覚えた後でも、ストレスや環境の変化によって排泄場所が一時的に乱れることもあります。
特に複数の個体を飼っている場合は、トイレの場所をめぐっての争いなどから、あちこちで排泄されるリスクも高くなります。
ニオイの主な原因②|巣材や床材の汚れ
巣材や床材が汚れてくると、それ自体が臭いの元になります。
ラットは自分のにおいがついた巣材に安心感を持つ傾向があり、同じ場所に何度も戻ったり、フンをため込むような行動を取ることもあります。
そのため、見た目がそれほど汚れていなくても、実際には臭いが蓄積されているケースも少なくありません。
とくに湿気を含んだまま放置すると、床材の中でバクテリアが繁殖し、カビのような匂いまで発生することもあります。
紙やウッドチップなどの素材によっても、ニオイのこもりやすさは変わります。
例えばウッドチップは吸湿性が高い一方で、時間が経つと独特の発酵臭のようなニオイを発することがあります。
清潔な床材を定期的に交換し、湿度が高くなりすぎないようケージ内の空気を循環させることが、ニオイの蓄積を防ぐポイントとなります。
ニオイの主な原因③|ケージの通気性が悪い

ケージの設計や置き場所もニオイの強さに関係します。
特に通気性が悪い場所にケージを置いていると、空気がこもって臭いが蓄積されやすくなります。
ファンシーラットが出す排泄物や皮脂のにおいは、本来であれば空気の流れとともに分散していくものですが、密閉された空間ではそれがうまくいきません。
その結果、部屋全体が動物臭で満たされてしまうということも。
また、ケージの素材にも注意が必要です。
例えばプラスチック製のケージは軽量で扱いやすい反面、通気性が悪く、臭いがこもりやすい傾向があります。
一方、金網タイプのケージは風通しが良く、臭いも外に逃げやすいためおすすめです。
ただし、通気性が良すぎると冬場は寒くなるため、季節に応じた対策も重要です。
ケージの置き場所としては、窓の近くや空気の流れがある場所が理想的です。
エアコンの風が直接当たる場所は避け、定期的な換気も忘れないようにしましょう。
ニオイの主な原因④|食べ残しの腐敗臭
食べ残した野菜や果物が放置されると、すぐに腐って嫌な臭いを発します。
特に湿気の多い時期や、室温が高い季節には腐敗のスピードが速まり、わずか数時間で強い臭いを放つこともあります。
ファンシーラットは好奇心旺盛で、食べ物をケージの隅や巣箱の中など、飼い主から見えにくい場所に持って行って隠すことがよくあります。
こうした「隠しエサ」が腐敗の原因となり、ニオイの元になっていることも多いです。
そのため、エサのあげ方にも工夫が必要です。
一度に大量に与えるのではなく、食べきれる量を小分けにして与えるようにすると、腐敗リスクを下げることができます。
毎日のチェックと、エサ場や巣箱の中の点検を習慣づけましょう。
さらに、腐敗したエサをそのままにしておくと、バクテリアや虫が発生する恐れもあります。
健康面にも悪影響があるため、ファンシーラットが快適に暮らせるよう、清潔な環境を維持することが大切です。
ファンシーラットの臭いを抑える7つの対策

・ケージの掃除はどれくらいの頻度が理想?
・消臭効果の高い床材
・飼育スペースの換気
・おすすめの消臭グッズとその使い方
・食生活の見直しで体臭も変わる?
・ファンシーラット自身の体を拭いてあげるべきタイミング
・多頭飼いで臭いが強くなるときの対処法
・ファンシーラットは臭いのか? まとめ
トイレのしつけで臭いを軽減
ファンシーラットは知能が高く、トイレの場所を覚えることも可能ですが、必ず覚えるとは限りません。
個体差が大きく、すぐに覚える子もいれば、なかなか覚えない子もいます。
性格や年齢、飼育環境の違いによっても、トイレを覚えるスピードには大きな幅があります。
しつけの基本としては、トイレ用のコーナーを明確に用意し、そこに吸水性の高い床材、または新聞紙を敷いておくことが大切です。
排泄を確認したら、その床材を使って匂いを残し、トイレ場所として認識させる方法が有効です。
また、トイレ以外で排泄した部分はすぐに掃除してにおいを消し、そこがトイレではないとラットに学習させましょう。
一度トイレの場所を覚えたラットは、かなりの確率で同じ場所を使うようになりますが、それまでにはある程度の時間と根気が必要です。
おやつで褒めるといった正の強化を活用することで、覚えやすくなる場合もあります。
失敗しても怒らず、静かに元の場所に誘導することを意識しましょう。
ケージの掃除はどれくらいの頻度が理想?

最低でも週に2回の全体掃除、トイレ部分だけなら毎日軽く掃除するのが理想です。
特にトイレ周辺はアンモニア臭が強くなりやすいため、汚れた部分だけでも毎日拭き取るようにしましょう。
可能であれば、においがこもりやすい巣箱の中や隅のスペースもこまめにチェックする習慣をつけると安心です。
さらに、床材が湿ってきたらすぐに交換することも忘れてはいけません。
湿った床材はバクテリアの温床となり、悪臭だけでなく病気の原因にもつながります。
湿気を防ぐためには、ケージの配置にも工夫が必要です。
直射日光が当たらない通気性の良い場所に置くことで、カビや菌の繁殖を抑えることができます。
また、ケージ掃除の際には消臭効果のある洗剤や除菌スプレーを使うと、においの再発を予防しやすくなります。
ただし、ラットの健康を考慮し、必ずペット用の無香料・低刺激性の製品を使用するようにしましょう。
月に一度はケージ全体を丸洗いして、付着した皮脂や汚れをしっかり落とすことが推奨されます。
金網部分やプラスチックトレーの隙間には汚れがたまりやすいので、古い歯ブラシなどを使って丁寧にこすり洗いすると効果的です。
その後はしっかり乾燥させてから再び設置することで、湿気やカビの発生を防ぐことができます。
ファンシーラットが健康的に過ごすためには、常に清潔な環境を保つことが何よりも重要です。
こまめな掃除を習慣にすることで、ラットとの生活がより快適でにおいの少ないものになります。
消臭効果の高い床材

ファンシーラットの飼育において、床材選びはニオイ対策の中でも非常に重要なポイントです。
私のおすすめの床材はハムキュートです。
ハムキュートは、優れた吸湿性と消臭効果を持っており、アンモニア臭や皮脂のにおいを吸収してくれます。
これにより、ケージ内の空気がより清潔に保たれ、飼い主にも快適な空間を提供することができます。
リアちゃんの床材が先週からハムキュートの消臭ペーパーマットになりました。KAMIYUKAは粉塵が全く出なくて良かったのですが床材同士が絡み合わないので潜りにくかったみたいで消臭ペーパーマットに変えてからまたよく潜っていて楽しそうです。カジカジも少し落ち着いたかな? pic.twitter.com/2RCFNVpRbc
— ともすたー (@tomoster_jan) July 5, 2020
また、ペレット状の床材は掃除がしやすく、汚れた部分だけを取り除くことができるため、経済的にも優れています。
紙製素材の中には再生紙を使ったエコタイプもあり、環境にも優しい選択肢となります。
季節やラットの性格に応じて、床材の種類を使い分けるのも効果的です。
飼育スペースの換気
飼育している部屋の空気の流れをよくすることも重要です。
空気がこもると、どんなに清潔にしていてもニオイが滞留しやすくなってしまいます。
窓を定期的に開けて外気を取り入れたり、サーキュレーターや扇風機で空気を循環させることも効果的です。
さらに、空気清浄機を設置することで、ニオイの原因となる微粒子やアレルゲンを取り除くことができます。
ペット用のフィルターが付いた空気清浄機なら、より効率的に空気中の不快な成分を除去してくれます。
エアコンを使う場合でも、換気モードを活用したり、部屋のドアを少し開けておくなど、密閉状態を避ける工夫が求められます。
このように、床材と空気環境の見直しは、ファンシーラットとの生活をより快適に、そして清潔に保つための鍵となります。
おすすめの消臭グッズとその使い方

市販の消臭スプレーや、消臭マットなどを使うことで、ケージ周辺のニオイを軽減することができます。
消臭スプレーは、ケージの外の臭いが気になるところに使用することで、ニオイ成分を中和し、空間を快適に保つ効果があります。
特に、植物成分のスプレーは安心して使えます。
消臭マットは、ケージの下に敷いて使用するタイプや、巣箱の中に入れるクッションタイプのものなど、さまざまな種類があります。
これらはアンモニアなどの臭いを吸収し、空間全体のニオイを軽減する効果があります。
なるべく植物由来のものを選び、日常的に使っても安心なものを優先しましょう。
食生活の見直しで体臭も変わる?
脂っこいエサや添加物の多いおやつは、ファンシーラットの体臭を強くする原因になることがあります。
とくに脂質やタンパク質が過剰なフードを日常的に与えていると、皮脂の分泌が活発になり、体臭やケージ内のニオイが強まることがあります。
そのため、新鮮な野菜や果物、バランスの取れた専用ファンシーラットフードを中心とした食生活に見直すことで、体臭を大きく軽減できる場合があります。
また、野菜や果物も水分が多すぎると下痢やニオイの原因になることがあるため、与える量や頻度には注意が必要です。
さらに、水の質も見直すポイントです。
カルキの少ない新鮮な水を毎日交換することで、体内環境の改善につながり、体臭が自然と減少することがあります。
こうした食生活の改善は、健康面でも良い影響を与えるので、におい対策と合わせてぜひ取り入れてみましょう。
ファンシーラット自身の体を拭いてあげるべきタイミング

ラットは基本的に自分で体を清潔に保つ習性があります。
頻繁に毛づくろいをしており、他の個体にも毛づくろいをしてあげる「グルーミング行動」も見られるほどです。
しかし、そんなファンシーラットでも体臭が強くなってきたと感じる場面があります。
とくに換毛期や高温多湿な季節、あるいは年齢を重ねて自己グルーミングが不十分になった個体などは、被毛に皮脂がたまりやすくなります。
そうしたタイミングでは、温かく湿らせた柔らかいタオルで体を優しく拭いてあげると、皮脂や汚れが落ちて清潔さを保ちやすくなります。
このとき、ゴシゴシと強く拭かないことが大切です。
ラットの皮膚は非常に繊細なため、優しく包み込むようにして撫でるだけで十分です。
また、タオルの素材はなるべく柔らかい綿素材などを選び、ぬるま湯で湿らせたあと軽く絞って使用しましょう。
拭いたあとはしっかり乾燥させることも忘れてはいけません。
毛が濡れたままの状態が続くと、冷えや皮膚トラブルの原因になることがあります。
タオルドライの後に乾いたタオルで軽く拭いたり、ぬるめの風をあてるなどして素早く乾かしましょう。
また、頻繁に拭く必要はなく、においが気になるときや被毛が脂っぽく感じたときなど、必要に応じて行うのがポイントです。
適度に手入れすることで、ファンシーラット自身もストレスなく清潔さを保てます。
多頭飼いで臭いが強くなるときの対処法
多頭飼いをしている場合、当然ながら排泄物の量も増えるため、掃除の頻度は単独飼育よりも高くする必要があります。
特に複数のラットが同じケージで過ごすと、トイレの場所も広がりやすく、特定のエリアに排泄が集中しにくいため、においがケージ全体に広がってしまう傾向があります。
また、オス同士は縄張り意識が強く、匂いづけのためのマーキング行動が盛んになることがあります。
これによって皮脂の分泌量が増え、ケージ内や個体自体のにおいが強まることがあります。
これを防ぐには、個体ごとのスペースに余裕を持たせることが重要です。
ケージが狭すぎるとストレスからさらに匂いづけ行動が加速する恐れもあります。
床材も吸収性や消臭性の高いものを選び、湿気や汚れがこもらないようにすることが大切です。
消臭スプレーや空気清浄機の併用も、多頭飼いの環境では有効です。
多頭飼いを快適に保つためには、定期的な観察と細やかな手入れが欠かせません。
におい対策だけでなく、ラットたちのストレス軽減にもつながるため、環境全体を見直してみることが大切です。

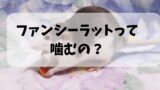
ファンシーラットは臭いのか? まとめ

結論として、ファンシーラット自体は強烈な体臭を持つ動物ではなく、適切な環境管理ができていれば、ほとんど気にならないレベルのニオイしか発しません。
しかし、掃除の頻度が少なかったり、通気性の悪い場所で飼育していたりすると、どうしてもアンモニア臭やカビ臭などが発生しやすくなります。
臭いが気になるときは、「どこに原因があるのか?」をしっかり見極めることが何より大切です。
トイレのしつけ、床材の選び方、換気、食生活、さらには多頭飼いの工夫まで、さまざまな視点から対策を講じることで、ニオイを大幅に抑えることが可能です。
そして何より、日々の小さなケアと観察が大切です。
ラットとの信頼関係を築きながら、お世話の時間を楽しむことができれば、自然と環境も整い、臭いの悩みも減っていくでしょう。
適切な環境と愛情をもって接すれば、ファンシーラットとの生活はとても快適で、豊かなものになるはずですよ。
ラット系の関連記事はこちらから!
「パンダマウスって共食いするの?」初心者が知っておくべき注意点と防ぐ方法




















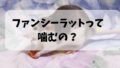
コメント