「ファンシーラットって可愛いけど、飼ったら後悔することってあるの?」
「SNSで見るラットはすごく懐いてるけど、実際はどうなの?」
「においや寿命、掃除の大変さって、本当のところどうなんだろう?」

そんな疑問や不安を持っている方に向けて、本記事ではファンシーラットを飼って後悔する理由と、後悔しないための準備や対策を詳しく解説します。
SNSでは魅力的に見えるペットでも、実際に飼ってみると「思っていたのと違った…」と感じることも少なくありません。
ファンシーラットも例外ではなく、性格や習性、飼育環境などをしっかり理解せずに迎えると、後悔につながることがあります。
この記事では、以下のようなポイントを押さえています:
✔ 夜行性やニオイなど、意外と見落としがちな注意点
✔ 後悔しないために準備しておくべきこと
✔ 飼い主の生活スタイルに合うかどうかの見極め方
この記事を読めば、ファンシーラットを「飼ってよかった」と思えるようになるためのヒントがきっと見つかります。
ファンシーラットを飼って後悔する理由

・想像以上に臭いが強くて後悔
・トイレのしつけが難しい
・夜中にうるさい
・寿命が短い
・ケージ掃除が想像以上に大変
・病気の診察をしてくれる病院が少ない
・旅行に行けない
・思ったより懐かない個体もいる
・周囲に理解されずらい
噛み癖がある
ファンシーラットは基本的に穏やかで人に懐きやすい性格とされていますが、すべての個体がそうとは限りません。
特に新しい環境に慣れていないうちは、警戒心が強く、驚いた拍子や防衛本能から噛むことがあります。
手を入れた瞬間に噛まれてしまった、エサをあげようとしたら噛まれたという声もあり、飼い主の接し方や環境に応じて注意が必要です。
噛み癖のあるラットは根気強く信頼関係を築くことが求められ、子どもと一緒に飼う場合は、最初から手渡しや接触を控えるなどの配慮が必要になります。
また、噛まれることで小さなケガをすることもあり、衛生面の対策も忘れてはいけません。
こうした行動に不安を覚える人は、飼育前に性格の個体差について十分な情報収集をしておくことが後悔を避けるカギになります。
少し休憩~🍵
待機中のファンシーラット🐭
個人的にこの左手が可愛くていい✨
可愛いとは言ってもケージの外から手を近づけたら噛まれるんだけどね💦ネズミ系はたまにそういう噛む癖のある子達がいるから、お迎えした最初の頃は気をつけてね。 pic.twitter.com/GFwxsKUThr
— 松本祐治(ブリーダーショップ空 店長) (@bs_kuu0726) July 23, 2022
ファンシーラットの噛み癖とその治し方についてはこちらを参考にしてください。
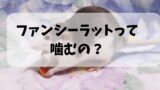
想像以上に臭いが強くて後悔

ファンシーラットは体臭自体は比較的少ないとされていますが、問題になるのは尿や糞のニオイです。
特にオスはマーキング行動をすることがあり、ケージ内に独特な強い臭いがこもる原因になります。
個体差はありますが、発情期には特に臭いが強くなることもあり、その際には掃除の頻度を増やす必要があります。
トイレの位置が定まらず、あちこちで排泄を繰り返すことで、掃除が追いつかずに臭いがたまりやすくなることもあります。
特に床材が湿気を含んだまま放置されると、雑菌が繁殖し、アンモニア臭がさらに強まります。
これに加え、床材や巣材に湿気がこもると、雑菌が繁殖してさらに臭いが強まることがあります。
湿度が高いと臭いの拡散も早く、狭い室内では一層気になりやすくなります。
特に夏場の高温多湿な環境や、換気の悪い場所では想像以上に臭いが広がりやすく、家族から不満が出ることも少なくありません。
来客時に気を使うという声もあり、生活空間とケージの距離感も重要なポイントです。
日常的な掃除に加え、空気清浄機の設置や消臭剤の活用、換気の徹底など、しっかりとしたニオイ対策を講じなければ、後悔する可能性が高まります。

トイレのしつけが難しい
ファンシーラットは犬や猫のように完全なトイレトレーニングが難しいため、あちこちに排泄してしまうことがあります。
トイレの位置を覚えてくれる個体もいますが、個体差があります。
さらに、ラットは習慣性があるため、一度排泄場所が決まるとそこに何度もするようになりますが、好みの場所がケージの端や巣箱の中だった場合、掃除が難しくなることも。
また、多頭飼いをしているとそれぞれの個体が好きな場所に排泄してしまい、トイレの統一が難しくなります。
専用トイレを設置しても、すぐには覚えてくれず、トレーニングには時間と根気が必要です。
そのため、トイレのしつけに過度な期待をせず、ある程度の排泄は許容しつつ掃除をしやすい環境づくりを心がけることが大切です。
夜中にうるさい

夜行性のため、飼い主が寝ている時間帯に活発に活動します。
昼間は大人しく寝ていることが多くても、夜になるとケージ内を走り回ったり、ホイールを回したり、カリカリと音を立てたりと意外と騒がしくなります。
静かな部屋にケージを設置していると、音が反響してさらに気になることもあります。
また、複数飼育している場合は、ラット同士のコミュニケーション音や争う音も加わり、眠れないという声も。
耳栓や防音ケージ、ケージの置き場所の工夫などが必要になるかもしれませんが、それでも完全に音を防ぐのは難しく、生活への支障を感じて後悔する人も少なくありません。
寿命が短い
ファンシーラットの平均寿命は2〜3年と短く、あっという間にお別れの時が来てしまいます。
懐いてきた頃には老化が始まり、病気がちになってしまう個体も多く、看取りの期間が急に訪れることも。
特に初めて飼育する方や、ペットとの別れに慣れていない方にとっては、別れの喪失感が大きく、「こんなに早くお別れがくるとは思わなかった」と後悔することがあります。
また、短命であるにもかかわらず日々の手間や愛情は他のペットと変わらず必要なため、時間と労力を注いだ分だけ心のダメージが大きくなることもあります。
寿命の短さを理解したうえで、限られた時間をどう過ごすかを意識することが大切です。
今日の夕方アルファが亡くなりました
1歳8ヶ月でした
初めてのファンシーラットで思い入れたくさん
ずっと小さくて可愛い子だった!悲しいなあ pic.twitter.com/WCN5H9XcjL— み (@PP_Alpha_Beta) April 6, 2025
ケージ掃除が想像以上に大変
糞尿の量が多く、特に複数飼育している場合は頻繁な清掃が必要になります。
床材がすぐに汚れてしまい、においの原因にもなるため、毎日の掃除が欠かせません。
週に1回の大掃除に加え、こまめな部分清掃も必要となることが多く、時間や労力を要します。
また、巣箱やホイール、給水ボトルなどの付属品にも汚れがたまりやすく、それぞれを定期的に分解して洗浄する手間も発生します。
ラットがトイレの位置を頻繁に変えることで、掃除の効率が悪くなり、ストレスを感じる飼い主もいます。
清潔な環境を保つためには計画的な掃除のスケジュールや、掃除しやすいケージ構造の選定も重要になります。
忙しい生活の中でこれらの手間が重なると、飼育が負担に感じられ、後悔につながるケースも少なくありません。
病気の診察をしてくれる病院が少ない
ファンシーラットを診てくれる動物病院は限られており、近所に専門の病院がないと通院が難しくなります。
特にエキゾチックアニマルに分類されるラットは、一般的な犬猫専門の動物病院では診てもらえないことも多く、いざというときに困るケースがあります。
病気の早期発見や適切な治療のためには、ラットの扱いに慣れた獣医師がいる病院を事前に調べておく必要がありますが、それ自体が手間に感じる人も。
さらに、診察料が比較的高めに設定されている場合もあり、経済的な負担も無視できません。
予防医療の知識を自分で学ぶ必要もあるため、ペット初心者にはハードルが高く、後悔する要因となりがちです。
旅行に行けない
短期間の旅行であっても毎日の世話が必要なため、預け先を探すのが難しいことがあります。
ラットはデリケートで環境の変化に弱く、ペットホテルでの対応が難しいことが多いため、簡単に預けることができません。
知人に世話を頼むにも、専門的な扱いに慣れていないと健康を損なうリスクもあります。
さらに、給水ボトルの不調やエサの補充忘れといった些細なトラブルが命に関わることもあるため、旅行中も安心できないという声も。
長期の外出や頻繁な出張がある人には不向きなペットといえるかもしれません。
思ったより懐かない個体もいる
SNSでは懐いたラットの映像が多く出回っており、手のひらの上で寝ていたり、名前を呼んだら寄ってくる様子など、理想的な姿ばかりが目につきます。
しかし実際には、警戒心が強く、人に慣れるまでにかなりの時間がかかる個体もいます。
特にペットショップから迎えたばかりのラットは、人との接触に慣れておらず、最初は近づくだけで逃げてしまうことも。
中には人の手を嫌がり、抱っこを極端に嫌がる子もいます。信頼関係を築くには、毎日の丁寧な声かけやおやつを使ったコミュニケーションなど、地道な努力が必要です。
それでも個体によっては最後まで距離感を保ったままになることもあり、SNSで見たような懐き方を期待していた人にとっては、ギャップにショックを受けることがあります。
こうした個体差を理解し、「懐くこと」だけを目的にしない飼育スタイルが求められます。
周囲に理解されずらい
「ネズミを飼っている」と言うと、驚かれたり嫌悪感を持たれたりすることも。
ファンシーラットは清潔で賢く、愛情深いペットであるにもかかわらず、「ネズミ=不衛生、害獣」といったイメージが根強く残っているのが現実です。
そのため、飼っていることを公に話すのをためらったり、親や友人に引かれてしまうのではと心配したりする人もいます。
家族から飼育を反対されるケースもあり、理解されないまま孤独な気持ちで世話を続けることにストレスを感じることも。
また、SNSでの発信も炎上や心無いコメントを受ける可能性があり、ラット飼い主同士でつながるコミュニティを見つけることが精神的な支えになるケースも多いです。
周囲の反応に傷つく前に、自分がなぜラットを飼いたいのかをしっかり見つめ直すことも大切です。
ファンシーラットを飼って後悔しないために

・飼い主の生活スタイルとの相性を見極めよう
・ニオイ対策にはこのアイテムが効果的
・糞尿対策と床材選びのコツ
・ケージは広く・静かな場所に設置しよう
・動物病院を調べておく
・1匹飼いと多頭飼い、どちらが向いている?
・愛情は伝わる!懐くための接し方とは
・お別れを前提にした「命との向き合い方」
・後悔しない人がしている日々の工夫とは?
・ファンシーラットを飼って後悔? まとめ
飼育前に「ファンシーラット」の特徴を理解する
夜行性、生態、性格、寿命などをしっかり調べてからお迎えしましょう。
特に、夜行性という生活リズムは、人間の活動時間帯とは逆になるため、夜中に騒がしくなることを理解しておく必要があります。
また、社交的で懐きやすいといわれる一方で、警戒心が強く個体差も大きいため、すぐに懐くとは限りません。
寿命が2〜3年と短いことも知っておくべきポイントで、お別れが早く訪れるという現実を受け入れる心構えも大切です。
さらに、トイレトレーニングが難しいこと、清掃頻度が高いこと、病院探しの手間など、日々の飼育に伴う苦労についても事前に理解しておくことで、「思っていたのと違った」というギャップを減らし、後悔のない飼育が可能になります。
飼い主の生活スタイルとの相性を見極めよう

日中は家にいない、静かに眠りたいなど、自分の生活リズムと照らし合わせて無理がないか確認しましょう。
ファンシーラットは夜行性のため、夜中に活動する音が気になる人や、静かな環境で眠りたい人にはストレスになることがあります。
また、毎日の掃除や餌やり、健康チェックなど、意外と手がかかるため、忙しくて家にいる時間が少ない人には負担が大きくなる可能性もあります。
加えて、ラットとのスキンシップを重ねることで信頼関係が築かれていくため、コミュニケーションに時間をかけられるかどうかも重要なポイントです。
休日にまとめて世話をしようとすると、ラット側にストレスがかかってしまうこともあるため、日々の生活の中に無理なくラットとの時間を組み込めるかを見極めてから飼い始めることが大切です。
ニオイ対策にはこのアイテムが効果的
脱臭効果のある床材、専用トイレ砂、など、臭い対策グッズをうまく活用することで快適に。
特に消臭液は、尿のアンモニア臭をしっかり吸収してくれるためおすすめです。
植物由来100%でペットにも人にもOKと書いてありますが、念の為、ファンシーラットにかけるのではなく、クサイ臭いが来てほしくないところや、ケージの近くのクッションなど、どうしても臭くなってしまうところに使うようにしましょう。
また、定期的な換気と組み合わせることで、より清潔な空間を保てます。
さらに、ケージ周辺を清潔に保つことでニオイの発生源を減らすことができ、飼育環境全体の快適さにもつながります。
糞尿対策と床材選びのコツ
吸収性の高い床材を選ぶことで掃除がラクになります。
新聞紙やウッドチップなど、コストとのバランスも考慮しましょう。
トイレ砂は交換しやすく、吸湿性・消臭性の高いものを選ぶと、衛生面の維持がしやすくなります。
床材はこまめに交換することが重要で、1日〜2日での交換を習慣にすることでニオイや雑菌の発生を抑えることができます。
また、汚れた部分だけを取り除ける部分清掃用のスコップやピンセットを常備しておくと日常的なお手入れがスムーズになります。
ケージは広く・静かな場所に設置しよう

十分な広さがあるケージを選び、落ち着いて過ごせる静かな場所に設置することでストレスを減らせます。
ファンシーラットは非常に敏感な動物で、騒がしい場所や日常的に人の出入りが多い環境では安心して過ごせません。
ケージの広さも重要で、狭すぎると運動不足やストレスにつながり、健康状態にも悪影響を及ぼすことがあります。
複数飼いの場合は、それぞれが十分に動けるスペースを確保する必要があります。
また、直射日光や冷暖房の風が直接当たる場所も避け、室温や湿度の管理がしやすい静かな空間を選ぶことで、より快適な生活環境が整います。
音や振動を感じにくい場所に置くことも、ラットの心の安定につながります。
動物病院を調べておく
事前にラットを診察してくれる病院を探しておきましょう。
口コミやSNSも活用しておくと安心です。
特にラットは病気の進行が早いため、体調の異変に気づいたらすぐに診てもらえる環境が必要です。
普段から健康診断をしてくれるか、緊急時に対応してもらえるかを確認し、診察時間や休診日もチェックしておきましょう。
また、獣医師との相性や対応の丁寧さも重要なポイントです。
地域によっては対応病院が限られるため、多少距離があっても信頼できる病院を確保しておくことで、いざというときの不安を軽減できます。
1匹飼いと多頭飼い、どちらが向いている?
ラットの性格や飼い主の経験値により、向き不向きがありますが、基本的にラットは群れで生活する社会性の高い動物です。
そのため、1匹だけで飼うとストレスを感じてしまう場合もあり、理想的には多頭飼いが推奨されます。
仲間と一緒に過ごすことで、安心感を得られたり、自然な行動が引き出されるため、より健全な飼育環境が整います。
ただし、相性の悪い個体同士を無理に同居させると争いが起きるリスクもあるため、初めて飼う場合は1匹から始めて徐々に様子を見ていくのが無難です。
愛情は伝わる!懐くための接し方とは
手からおやつを与える、優しく話しかけるなど、毎日少しずつ信頼関係を築いていくことが大切です。
ラットは繊細で賢い生き物なので、飼い主の声や匂い、触れ方をしっかり記憶します。
はじめのうちは警戒心を持って距離を置くこともありますが、根気よく優しい対応を続けることで徐々に心を開いてくれるようになります。
急に抱っこをしようとしたり、大きな音を立てると警戒されやすいので、静かで落ち着いた環境づくりも大切です。
また、ラットは社会性が高いため、毎日少しの時間でも一緒に過ごすことで、より信頼関係を深めることができます。
時間と愛情を惜しまずに接することで、自ら寄ってきたり、甘えてくるようになる個体も多く、飼い主としての喜びを感じられる瞬間が増えていきます。
お別れを前提にした「命との向き合い方」
寿命が短いからこそ、限られた時間を大切に。
ペットロスへの備えや心構えもしておきましょう。
ラットとの暮らしは多くの喜びをもたらしますが、そのぶん別れの瞬間はとてもつらいものです。
突然の体調不良や老化に直面すると、心の準備ができていなかったことに後悔することもあります。
あらかじめ寿命の短さを理解し、健康管理に努めながら、できる限りの愛情とケアを注ぐことで、「もっとこうしてあげればよかった」という気持ちを少しでも減らすことができます。
亡くなったあとに写真を飾ったり、思い出を記録したりすることで、ラットとの絆を心の中に残すことができ、癒しにもつながります。
大切な命と向き合う覚悟を持つことが、ペットと豊かな時間を過ごす第一歩です。
後悔しない人がしている日々の工夫とは?
掃除や健康チェックをルーティン化、ラットとの時間を習慣にするなど、小さな工夫の積み重ねが快適な飼育生活を支えます。
たとえば、毎朝同じ時間に声をかけて様子を見る、ケージ内の汚れをその都度チェックしてすぐに清掃する、エサや水の補充をタイマーアラームで忘れず管理するといった行動です。
また、季節ごとの温湿度の変化に合わせた環境調整や、月に一度の健康記録をノートにつけておくなど、日々の中で継続できる仕組みを作っておくと、無理なく続けやすくなります。
こうした些細な積み重ねが、ラットとの信頼関係や健康を保つうえで大きな効果を発揮し、結果的に「飼って良かった」と感じられる生活へとつながっていきます。
ファンシーラットを飼って後悔? まとめ

ファンシーラットは小さくて愛らしく、知能も高いため魅力的なペットとして多くの人に親しまれています。
しかし、その可愛さだけに惹かれて勢いで飼い始めてしまうと、思わぬギャップに直面し、後悔することもあるかもしれません。
飼う前には、夜行性であることや寿命の短さ、掃除やニオイ対策、さらには医療面や旅行中の対応など、リアルな面もしっかり理解しておくことが大切です。
飼育環境を整え、自分のライフスタイルとの相性を見極めながら、情報を十分に集めたうえで迎えることが、後悔のないラットライフへの第一歩です。
自分に合った飼育スタイルを見つけて、ラットとの豊かな日々を過ごしましょう。
小動物の関連記事はこちらから!!
「パンダマウスって共食いするの?」初心者が知っておくべき注意点と防ぐ方法
「アフリカヤマネがうるさい…そんな悩みを解決する7つの対策」





















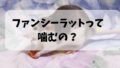
コメント