「ナマズは本当にペットとして飼えるの?」
「ナマズってどれくらい大きくなるの?」
「ナマズを飼ってみたいけど、飼育の難易度はどれくらい?」

そんな疑問を持っている方に向けて、本記事ではナマズの飼育について詳しく解説します。
私は10年以上ナマズを飼育してきましたが、実際に飼ってみると予想以上に面白く、奥が深い生き物だと感じました。
ナマズは比較的丈夫な魚でありながら、大型に成長するため適切な環境が必要です。
エサや水槽の準備、ろ過装置の選び方、屋外での飼育方法など、初心者が気をつけるべきポイントを押さえながら、ナマズの魅力についてもお伝えしていきます。
記事のポイント
✔ ナマズは適切な環境を整えればペットとして飼育可能
✔ 一般的なナマズは成長すると50~60cmほどになる
✔ ナマズは肉食性が強く、エサの種類に注意が必要
✔ 水質管理が重要で、ろ過装置や定期的な水換えが必須
✔ 混泳には注意が必要で、基本的には単独飼育が推奨される
それでは、ナマズの飼育方法について詳しく見ていきましょう!
ナマズの飼育

・ナマズの寿命は?
・ナマズの成長速度
・ナマズの餌
・ナマズってなつく?
・混泳してもいい?
・ナマズに最適な水温
・ナマズを屋外で飼育してもいい?
・トロ舟で飼育してもいい?
ナマズってどんな魚?
ナマズは日本の川や湖に生息する淡水魚で、夜行性のため主に夜に活動します。
口元に生えたヒゲで水中のエサを探る特徴があり、肉食性が強く、小魚や昆虫を好んで食べます。
また、ナマズは泥底の環境を好み、水質の変化にも比較的適応力がある魚です。
自然界では雨の前に活発に動くことが知られており、釣り人の間では天候とナマズの行動が関連しているといわれています。
ナマズは種類も豊富で、日本にはマナマズやイワトコナマズなどが生息しており、それぞれ異なる生息環境に適応しています。
また、海外にはレッドテールキャットやプラーチョンなど、非常に大型になる種類も存在し、観賞魚としても人気があります。
ナマズの寿命は?

飼育環境によりますが、平均寿命は10~15年程度です。
適切な環境とケアを提供することで、長く健康に育てることができます。
特に水質管理が寿命に大きく影響するため、ろ過設備の整備や定期的な水換えが重要です。

私が飼育していたナマズも、10年以上元気に過ごしていました。
ナマズの寿命は個体差があり、自然界では捕食者や環境の影響を受けるため、飼育下よりも短命になることが多いです。
しかし、適切な温度管理やバランスの良い食事を提供することで、最大で20年ほど生きる個体も報告されています。
特に、適切なろ過と定期的な水換えを怠らず、ストレスの少ない環境を作ることが、長寿の秘訣です。
ナマズの成長速度
ナマズは成長が早く、種類によって異なりますが、1年で20cmほどに、2〜3年で30cmまで育つことが多いです。
飼育環境によって成長スピードが変わることがあり、水槽の大きさやエサの量、栄養バランスによっても影響を受けます。
特に、大型水槽で十分なスペースを確保すると、より大きく健康的に育ちます。
| 年齢 | 成長サイズ (cm) | 影響要因 |
|---|---|---|
| 1年 | 20cm | エサの質と量、水槽サイズ |
| 2年 | 30cm | 水温、水質管理 |
| 3年 | 40cm | 水槽の広さ、隠れ家の有無 |
| 4年 | 50cm | 個体差、成長の停滞期 |
| 5年 | 60cm | 環境による最終サイズ決定 |

私の経験では、狭い環境では成長が抑制されることがあり、広い環境で飼育することがナマズの成長には不可欠でした。
実際に、45cm水槽で飼育していた個体と90cm水槽で飼育していた個体では、後者のほうが圧倒的に成長が早く、大きくなりました。
また、餌の種類によっても成長に差があり、高タンパクな生き餌や冷凍エビを与えると成長が促進される傾向があります。
さらに、ナマズは環境の変化に敏感なため、急激な水温の変化や水質の悪化が成長に影響を与えることがあります。
そのため、適切なフィルターを使用し、水換えの頻度を適切に管理することが重要です。
特に幼魚期には成長が著しく、最初の1年で急速に大きくなるため、この時期のエサと環境管理がナマズの将来のサイズを左右します。
ナマズの餌

ナマズは肉食性が強いため、小魚、エビ、昆虫などを好んで食べます。
飼育下では冷凍エサや人工飼料にも慣れます。

私が飼っていたナマズは、最初は生きエサばっか食べていましたが、慣れればペレットにも食いつくようになりました。
また、食事のバリエーションを増やすことで、ナマズの健康を維持しやすくなります。
例えば、冷凍アカムシやドジョウ、カエルの肉などを与えると、より自然な食生活に近づけることができます。
ナマズのエサは種類によっても適性が異なります。
例えば、マナマズは昆虫や甲殻類を好む傾向がありますが、レッドテールキャットなどの海外産ナマズは魚肉をより多く摂取することを好むことが多いです。
また、ナマズは嗅覚が非常に発達しており、匂いの強いエサに反応しやすいので、においの強いエビや魚の切り身を与えると食いつきがよくなる傾向があります。
ナマズの成長期には高タンパクな食事が重要ですが、成魚になると脂肪の蓄積を避けるために食事の回数を減らすことが推奨されます。

私の経験では、幼魚のうちは1日2回のエサやりが効果的でしたが、成魚になると2~3日に1回に減らしたほうが健康的でした。
また、食べ残しが水質悪化の原因となるため、適量を見極めながら与えることが大切です。
エサの与え方にも工夫が必要です。ナマズは夜行性のため、日中よりも夜間にエサを与えるほうが自然な生活リズムに合い、ストレスを軽減できます。
また、水槽に流れを作ることで、エサが水中に自然に漂い、ナマズが狩りをするようにエサを食べることができるため、より健康的な食生活を送ることができます。
さらに、ナマズは水質の変化に敏感なため、エサの与えすぎによる水質悪化には特に注意が必要です。
特に油分の多いエサ(サーモンや脂の多い魚肉)は水を汚しやすいため、頻繁な水換えが必要になります。
エサの種類を変えることで水質の維持もしやすくなるため、ナマズの健康を守るためにさまざまなエサをローテーションしながら与えるのも有効です。
ナマズってなつく?


個体によっては飼い主に慣れ、エサの時間になると寄ってくることもあります。
私が飼育していたナマズも、手を水槽に近づけると反応して寄ってきました。
特にエサを手から与える習慣を続けることで、ナマズとの距離を縮めることができます。
ただし、無理に触れようとするとストレスを感じることがあるので注意が必要です。
ナマズは視力が弱く、動きに敏感に反応するため、特定の音や振動にも慣れることがあります。
ナマズの個体差によっては、特定の動作や音に反応するものもいます。
例えば、私のナマズは水槽のガラスを指で軽く叩くと寄ってくることがありました。
これは、ナマズが学習能力を持っていることを示しています。
ナマズは警戒心が強い魚ですが、時間をかけてゆっくりと接することで、よりリラックスした関係を築くことができます。
水槽の環境を整え、ストレスの少ない環境を維持することで、ナマズが人に慣れるスピードも速くなるでしょう。
混泳してもいい?
ナマズは肉食性が強いため、小型魚との混泳は避けたほうが無難です。
特に口に入るサイズの魚は捕食される可能性が高いため、注意が必要です。
大型でおとなしい魚との相性は良いこともありますが、基本的には単独飼育が推奨されます。
私は同じサイズのナマズを2匹一緒に飼っていましたが、トラブルなく共存できていました。
ただし、縄張り意識が強い個体もいるため、複数飼育する場合は広めの水槽を用意することが重要です。
隠れ家を増やすことで、ストレスを軽減することができます。
また、水槽内の流れを工夫することで、テリトリーの問題を最小限に抑えることができます。
ナマズは基本的に夜行性なので、昼行性の魚との混泳はトラブルになりにくいですが、夜間に動き回るため、寝ている魚を驚かせることがあります。
これにより、ストレスが溜まりやすい魚種との組み合わせは避けたほうがよいでしょう。
ナマズに最適な水温

ナマズは幅広い水温に適応できますが、15~25℃が理想的です。
急激な水温変化はストレスになるため、ヒーターや冷却ファンを活用して安定した環境を維持しましょう。
特に夏場は水温が上がりすぎないように注意が必要です。
夏場は30℃近くになると活動が鈍くなることがあるため、冷却ファンや日陰を活用して適切な温度管理を行うことが重要です。
また、水温が安定しないとナマズが病気にかかるリスクが高まるため、長期間安定した環境を整えることが大切です。
ナマズは種類によって適温が異なる場合があります。
例えば、日本のマナマズやイワトコナマズは比較的低温にも耐えられますが、アマゾン原産のレッドテールキャットフィッシュは25℃以上を好むため、水槽の設定温度を適切に管理する必要があります。
また、水温の変化が活発な環境では、ナマズの活性が変化することがあります。
これをうまく利用し、適切な時期に栄養価の高い餌を与えることで、健康な成長を促すことができます。
ナマズを屋外で飼育してもいい?

ナマズは寒さにある程度耐えられるため、屋外飼育も可能です。
ただし、冬場の極端な低温や夏の水温上昇には注意が必要です。

私も屋外で飼育していたことがありますが、冬は水深を深くして水温の変化を抑えるように工夫しました。
また、屋外での飼育では、天敵の存在にも注意が必要です。
特に鳥や猫などの捕食者がナマズを狙うことがあるため、水槽や池の上にネットを張るなどの対策を講じると安全です。
さらに、屋外では日光が直接水面に当たるため、藻の発生が増えることがあります。
水質の悪化を防ぐために、定期的な水換えと、水槽の影になる場所を作ることが重要です。
夏場には水温が急上昇することがあるので、適度に日陰を作ったり、水温が上がりすぎた場合は一部水を入れ替えるなどの工夫をするとよいでしょう。
屋外飼育のメリットとしては、自然の気温変化に適応しやすくなる点があります。
ナマズは変温動物のため、外気温の影響を受けやすいですが、適切な環境を整えることで、健康的に育てることができます。
また、屋外の広い環境では成長が早くなる傾向があるため、より大きなナマズを育てたい場合には適しています。
トロ舟で飼育してもいい?
トロ舟(大型プラスチック容器)での飼育も可能です。
水質管理を適切に行えば、屋外でも健康に育てられます。
トロ舟は水量が多いため水質が安定しやすく、屋外飼育には適した設備ですが、注意点もあります。
特に夏場は水温が上昇しやすいため、日除けを設けたり、日陰に設置する工夫が必要です。
私の経験では、トロ舟を直射日光の当たる場所に置いていたとき、水温が30℃以上になり、ナマズの動きが鈍くなったことがありました。
そのため、午前中は日が当たり、午後からは日陰になるような場所に移動することで、水温を適度に保つことができました。
また、トロ舟は水深が比較的浅いため、冬場の冷え込みに弱いというデメリットもあります。
冬季には水深を確保するか、断熱材を敷くことで冷え込みを防ぐ対策が必要です。
私は発泡スチロールをトロ舟の周囲に巻いて断熱し、寒さ対策を行っていました。
トロ舟の管理には定期的な水換えが重要で、特に屋外では雨水の影響で水質が変化しやすくなるため、pHやアンモニア濃度をチェックすることも推奨されます。
適切な環境を維持することで、屋外でも快適にナマズを育てることができます。
ナマズ。これぞ定番種。なのに誰もポストしてない。非常に飼育しやすく、飛び出しにさえ気をつければ気にする事もなく、精神的にも安心できるナマズ。 #ナマズ超図鑑 pic.twitter.com/TfWhOhnC0Y
— RK (@off_the_lock_RK) October 12, 2024
ナマズの飼育に必要なもの

・ろ過フィルター
・隠れ家
・飼育しやすい小型のナマズ
・よくあるナマズの飼育トラブルとその対策
・ナマズの飼育Q&A
・私がナマズの飼育で苦労したこと
水槽とふた
ナマズは成長すると50cm以上になることがあるため、最低でも90cm以上の水槽が望ましいです。
水槽の大きさによっては100cm以上に成長する可能性もあるため、飼育スペースに余裕があるなら120cm水槽を選ぶのもおすすめです。
また、ナマズはジャンプする習性があるため、しっかりとフタをしましょう。
特に夜間は活発に動くことが多く、驚いた拍子に水槽の外に飛び出してしまうことがあります。
私自身も、何度かフタがしっかり閉まっていないことで脱走されたことがありました。
ろ過フィルター
ナマズは排泄量が多く、水が汚れやすいため、強力なろ過フィルターを用意しましょう。
外部フィルターや上部フィルターが特におすすめです。
ろ過能力が不足すると水質が急激に悪化し、病気のリスクが高まるため、通常よりも強力なろ過装置を選ぶことが重要です。
また、ナマズは底に溜まった餌の食べ残しや排泄物を巻き上げることが多いため、底面フィルターを併用するとより効果的に水質を維持できます。
さらに、ろ過装置に活性炭やゼオライトを入れることで、アンモニアや臭いを抑えることができます。
隠れ家
ナマズは暗い場所を好むため、水槽内に流木やシェルターを設置すると落ち着いて過ごせます。
特に幼魚の頃は臆病な個体が多く、隠れられるスペースがないとストレスを感じることがあります。
私の経験では、大型の土管や岩を配置することで、ナマズが安心して休めるようになりました。
流木や岩を使うと、水槽内の環境がより自然に近づき、ナマズの行動が活発になることが観察できます。
ただし、ナマズは成長が早いため、隠れ家のサイズも成長に合わせて調整する必要があります。
飼育しやすい小型のナマズ
大型のナマズの飼育が難しい場合、小型種を選ぶのもおすすめです。
小型ナマズは比較的おとなしく、小型水槽でも管理しやすい種類が多いです。ここでは、代表的な小型ナマズを紹介します。
ギギ

ギギは日本の河川に生息するナマズ科の魚で、最大でも20cm程度にしか成長しません。
流れの緩やかな環境を好み、隠れ家を用意すると落ち着きやすくなります。
性格は比較的おとなしく、単独飼育はもちろん、同種との混泳も可能です。
ただし、肉食性があるため、口に入るサイズの小魚とは混泳しない方が安全です。
アカザ

アカザは日本固有の小型ナマズで、清流に生息し、水質が良い環境を好みます。
最大でも10~15cmほどにしか成長せず、小型水槽でも飼育可能です。
体に毒を持つ棘があるため、取り扱いには注意が必要です。
人工飼料にも慣れやすく、比較的飼育がしやすいですが、水質の悪化に敏感なため、こまめな水換えが必要になります。
ウッドキャット

ウッドキャットは南米原産のナマズの仲間で、流木のようなユニークな見た目が特徴です。
サイズは10~15cmほどで、大型のナマズに比べて非常に小さく、管理がしやすいです。
性格は温和で、他の魚との混泳にも適しています。
夜行性で、昼間は流木や岩陰に隠れて過ごすため、隠れ家をしっかりと用意するのがポイントです。
よくあるナマズの飼育トラブルとその対策

ナマズの飼育ではいくつかのトラブルが発生することがあります。
ここでは、よくある問題とその解決策を紹介します。
水槽から飛び出す
ナマズはジャンプする習性があるため、フタをしっかり閉めることが重要です。
特に驚いたときや夜間に活発に動くため、フタに重りをつけたり、ロック機能のあるものを使用すると安全です。
水質悪化
ナマズは排泄量が多いため、水が汚れやすくなります。
定期的な水換え(週1回以上)と、ろ過装置のメンテナンスを徹底することで水質を安定させましょう。
底砂の掃除も忘れずに行い、エサの食べ残しが溜まらないように注意してください。
エサの食べ残しが多い
ナマズは夜行性で、エサの食べ方にムラがあります。
与える量を調整し、食べ残しが出ないようにしましょう。
また、フレークやペレットよりも冷凍エサや生餌のほうが食いつきがよい場合もあるので、エサの種類を見直すのも手です。
混泳相手を攻撃する
ナマズは肉食性が強いため、口に入るサイズの魚を捕食することがあります。
混泳を考える場合は、ナマズよりも大きな魚や、攻撃性の低い魚を選びましょう。
隠れ家を増やすことで、ナマズが攻撃する頻度を減らすことができます。
ナマズの飼育 Q&A

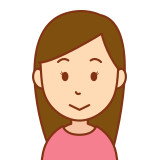
Q: ナマズはどれくらいの頻度でエサを与えればいい?

A: 幼魚なら1日1~2回、成魚なら2~3日に1回程度が目安。
ただし、ナマズは個体差があり、食欲にムラがあることもあります。
水温や季節によっても食べる量が変わるため、様子を見ながら適量を調整することが重要です。
特に冬場は活動が低下するため、エサの量を控えめにすると水質の悪化を防ぐことができます。
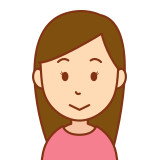
Q: ナマズはどのくらいの大きさまで育つ?

A: 一般的なナマズは50~60cmほどに成長。
ただし、環境によってはさらに大きくなることもあります。
屋外の池や大型水槽で飼育すると成長が早まり、70cm以上になるケースもあります。
また、種類によって成長速度が異なり、小型種のギギやアカザは15~20cm程度、ウッドキャットは10~15cmほどに留まります。
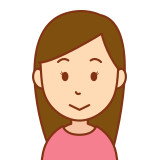
Q: 水槽のレイアウトはどうすればいい?

底砂はナマズの生態に合ったものを選ぶとよいでしょう。
細かい砂や丸みのある砂利を使うと、ナマズが底を這う際にヒゲを傷つけにくくなります。
また、隠れ家として流木や土管、シェルターを設置するとナマズが安心して休めます。
レイアウトは、ナマズが広々と泳げるスペースを確保しつつ、適度に物陰を作ることがポイントです。
私がナマズの飼育で苦労したこと
ナマズを10年以上飼育してきた中で、いくつか苦労したことがありました。
まず一つ目は、水槽からの脱走対策です。
ナマズは驚くほどジャンプ力が強く、夜中にフタを押し上げて水槽の外に飛び出してしまうことが何度かありました。
最初の頃はフタをしっかり閉めていたつもりでも、意外と隙間から抜け出してしまうこともありました。
中には、朝起きたら水槽から出てカピカピになっていたなんてことがありました。
持ち前の生命力でなんとか生存はしましたけど、最初に気づいた時は本当にヒヤヒヤしました。笑
そのため、フタの重さを増やしたり、クリップで固定するなどの工夫が必要でした。
2つ目は、水質の管理です。
ナマズは排泄量が多く、水質がすぐに悪化しやすいです。
特に成長するにつれて糞の量が増え、ろ過装置だけでは追いつかなくなり、頻繁な水換えが必要になりました。
最初は週1回の水換えで十分だったものの、大型個体になると2〜3日に1回は部分換水をしないと水が汚れてしまいました。
そのため、強力なろ過装置を導入し、底砂の掃除をこまめに行うことで水質の維持に努めました。
3つ目はエサの食べ残しと対応です。
ナマズはエサの食べ方にムラがあり、一度にたくさん食べるときもあれば、まったく食べない日もありました。
特に気温が下がる冬場は食欲が落ち、通常の量を与えると食べ残しが発生し、水質悪化の原因になりました。
気温が下がる冬場は、本当に食欲が落ちますが、それで大丈夫なんです。
あえて食べないのにあげたりしなくても大丈夫です。
エサの量を調整しながら、冷凍エサや生餌の種類を変えて食欲を刺激する工夫をしなければいけません。
ナマズの飼育 まとめ
ナマズは比較的丈夫な魚ですが、大型になるため、適切な環境を準備することが重要です。
長く健康に育てるために、水質管理やエサのバランスに注意しながら飼育を楽しみましょう。
ナマズは個体ごとに性格が異なり、警戒心が強いものもいれば、人懐っこくなる個体もいます。
時間をかけて接すると、エサの時間に寄ってくるようになったり、特定の行動パターンが見られたりするのもナマズ飼育の面白さの一つです。
また、ナマズの成長は環境によって大きく左右されます。
適切な水温管理と広いスペースを確保することで、より大きく健康的に育てることができます。
特に水槽の大きさやろ過装置の性能はナマズの健康維持に不可欠な要素です。
さらに、ナマズの飼育を続けることで、新しい発見があるのも魅力です。
私自身10年ほどナマズを飼育してきましたが、その間にナマズが水槽内の環境に適応する様子や、学習能力の高さに驚かされることが何度もありました。
特に、決まった時間にエサを与えると、その時間に活発に動くようになるなど、習慣化する行動が見られました。
これからナマズを飼う方にとって、少しでも役立つ情報となれば幸いです。
ナマズは長寿で丈夫な魚ですが、しっかりとした環境を整え、愛情を持って飼育することで、さらに魅力的な一面を発見できるはずです。
ぜひ、ナマズとの暮らしを楽しんでください!
関連記事はこちらから!!


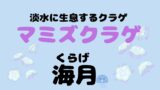






















コメント